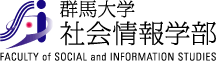大学院 社会情報学研究科の概要
1. 社会情報学研究科の理念・目標
本研究科は、社会情報学の深化と発展を図り、社会的・時代的な要請を受けて活躍することのできる「高度専門職業人」および「実践的研究者」を養成することを目的とします。
高度専門職業人とは、人文・社会科学、情報科学の知識とそれに基づいた社会的洞察力・状況分析能力・科学的思考能力を駆使して、行政・企業・NPOなどの各種組織において意思決定に具体的・実践的に関与できる人材を指します。
実践的研究者とは、社会情報過程の主体としての人間と情報化の共存という視点に立って、情報化の進展に伴う経済・社会・産業の諸問題や、地域社会における多様な組織の在り方を考究できる人材を指します。
2. 社会情報学研究科の教育・研究内容
本研究科は,「社会情報学専攻」の一専攻により構成されますが,複数の教育・研究領域を設定することで,大学院生それぞれのニーズと専門的な指導上の多様な必要性を有機的に結びつけながら学際的・総合的な指導に当たります。各領域は,伝統的な人文・社会科学の諸分野を情報科学という切り口で再編成して学際的に構成されており,社会情報学の研究の進展や学生の教育上の必要性,また情報化・国際化・地方分権化など現代社会の構造変動がもたらす高度専門教育への要請に対応するように設けられており,必要性を見極めて適宜編成し直されます。
3. 社会情報学研究科の構成
激変し続ける高度情報社会が次々と生み出す諸課題に対応する教育研究という広汎な社会的要請に応えるために、以下の7つの大きな研究領域が設定されています。
文化・コミュニケーション領域
高度情報社会における文化とコミュニケーションの現状と、そのあるべき姿を探求する領域です。高度情報社会は便利な情報メディアをわれわれに与えただけでなく、人と人とのコミュニケーションの在り方や文化や心理メカニズムの作用にかかわる人間的状況の深層構造をも変えていく可能性があります。このような状況的変化の様相を、文化論、心理学、社会学、メディア論、コミュニケーション論といった切り口から探求し、あるべき高度情報社会の姿についても構想する領域です。
経済・経営領域
経済・経営領域では経済政策や経営戦略を策定する研究を目指し、それを高度化するために情報活用と情報化対応の視点から取り組んでいきます。本領域は、経済・産業分野と経営・会計分野から構成されます。経済・産業分野では、経済構成主体の行動や経済活動全体を経済情報を利用しながら分析して、地域や国などの経済政策を産業の生産や消費・生活に注目して策定・評価する研究をします。経営・会計分野では、急速に変容しつつある経営環境(顧客環境・競争環境・技術環境・地球環境・組織環境等)に適応するために必要な経営情報過程の解析と経営的意思決定に関する実践的研究を行います。
地域・行政領域
高度情報社会における地域振興、行政機能のあり方および行政情報の意義を研究し、行政組織の意思決定に関する実践的教育研究を行います。具体的には、行政や地域に関わる情報社会に特有の諸問題を分析したうえで、地域社会学、行政学、行政法学、環境科学など地域と行政の在り方を問う領域と、地域における社会的起業やプロジェクトを実践するためのスキルを養成する領域を総合し、問題の解決のために求められる行政機関と公的サービスの役割を、市民の立場から提案するための研究を行います。
情報技術領域
先端的情報理論と、情報処理機器や情報ネットワークのいっそう高度な利用、情報システムやインターネットの構築と管理についての実践的研究を行います。
社会実証領域
高度情報社会現象の客観的把握と将来予測を行うための、データの収集法・分析法についての実践的研究、情報社会における諸社会現象の成因を社会調査結果や統計資料をデータ解析することにより実証する研究を行います。
社会モデリング領域
高度情報社会を様々な「システム」とその内外を流動する「情報」の総合体ととらえ、これらの仕組みと相互作用を、データ解析やシミュレーションによって解析する研究、および個人レベルでの意思決定と経営組織など集合的意思決定における理論と方法についての実践的研究を行います。
グローカル領域
高度情報社会のグローバルな発展と対になるはずの、日本の地域社会が衰退しつつある現状を打開するための、様々な地域活性化策の研究、および地域の新たな構成員である非日本語圏出身者の日本語学習と相互理解における、言語学的および日本語教育学的課題解決のための研究を行います。
これらの7つの研究領域は、社会情報学の誕生当初から人文・社会科学の諸分野を情報科学という共通のツールで再編成した学際的な各学問分野、および、既存の構成学問分野のさらなる融合や発展により形成されつつある新研究領域で構成されています。
日本初の社会情報学研究科であった本研究科設立後、多くの社会情報学研究科が他大学で設置されました。本研究科は社会情報学研究のフラグシップとして、激変し続ける高度情報社会が次々と生み出す諸課題に対応する教育研究を実行するという社会的要請に応えるために、これらの7つの研究領域を配置しました。
4. カリキュラムの構成
大学院生は必修科目群である「選択必修科目」「特別研究」と、これらと相互に連関性を持った「選択科目群」である「コース科目」および「共通基盤科目」に配置された、7つの「研究領域」に関する専門科目と、集中講義である「先端応用情報学領域」の科目のなかから、研究上の必要に応じて選択して学びます。これらの科目は、各研究領域に関連する問題や課題を、常に情報および情報社会との関わりを意識しながら分析し結論や解決策を提示するという、「社会情報学」に関する理念・知見・研究方法を学べるように配置されています。
- 特別研究
IおよびIIからなります。修士研究および論文作成に直接必要な指導を受けて課題研究を行います。主指導教員が開設する科目を受講しますが,これに加えて研究の必要に応じて,他の教員の開設する特別研究を受講することも可能です。 - 選択必修科目
社会情報学の研究に必須な人文・社会科学の理論等について学ぶ科目(比較社会情報学特論、理論社会学特論のいずれかを履修すること)、および修士論文作成スキルについて実践的に学ぶ科目(論文作成セミナー、受講内容は選択可能な必修)で構成されています。 - メディア社会構想コース科目
本コースでは、メディアへの着目を基礎に、望ましい新たな社会のあり方を構想します。本コースの「メディア」は、狭義のマスメディアやパーソナルメディアだけでなく、それを支える電子的な技術や人間本来の言語的・非言語的なコミュニケーション能力などを含むより広い概念です。また、「社会」には、法的、自然科学的な意味を含む広範な社会システムの意味を込めています。
高度情報社会におけるメディア・文化およびコミュニケーションの特質について学ぶ「文化・コミュニケーション領域」、情報化に伴い地域社会・行政に発生している諸課題と解決策について学ぶ「地域・行政領域」、高度情報社会のグローバル化と対になる地域社会の活性化や非日本語圏出身者との共生について実践的に学ぶ「グローカル領域」の3領域で構成され、研究上の必要に応じて選択して学びます。 - 社会システムデザインコース科目
本コースでは、社会実験・シミュレーションやデータ解析の結果に基づいて、社会システムをデザインできる能力を育成します。
高度情報社会における諸社会現象の成因を、社会調査結果や各種統計資料をデータ解析することにより実証する「社会実証領域」、情報社会を構成している様々な社会システムの構造・機能を数理モデルやシミュレーションにより分析する「社会モデリング領域」、高度情報社会における経済統計資料の分析や経済政策・経営戦略などについて学ぶ「経済・経営領域」の3領域で構成され、研究上の必要に応じて選択して学びます。 - 共通基盤科目
情報通信技術の高度な利用や情報システムやインターネットの構築と安全安心な管理について学ぶ「情報技術領域」、および社会情報学研究の最先端のトピックを学ぶ「先端応用情報学領域」で構成され、研究上の必要に応じて選択して学びます。
5. 充実のサポート体制
本研究科では,個々の大学院生の学修と研究の指導に際して,複数教員チーム(主指導教員1名及び副指導教員1~2名)による「個人別指導」を行います。これは,社会情報学の学際的性質と,大学院生がそれぞれ抱く学術的目標の個別性の調和を図り,それぞれの研究課題の達成をきめ細かく支援するための仕組みです。
また本研究科の講義は昼夜開講となっており,現職社会人院生が,仕事が終わってから夜間の授業時間帯のみの履修でも必要単位を修得できます。
大学院の入学から修了まで
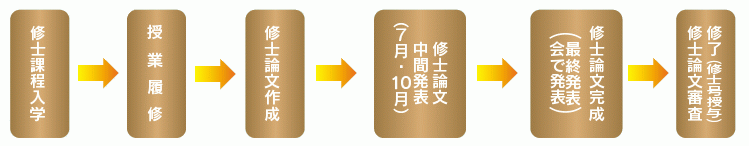
履修手引・学年暦・時間割
社会情報学研究科の令和3年度~の学年暦・時間割,平成29年度〜の履修手引は以下のPDFとして閲覧できます(履修手引きのPDFファイルはWeb掲載用の簡易版ですので,ご注意下さい)。
- 2023(令和5)年度社会情報学研究科時間割(2023年04月19日版)
- 2023(令和5)年度社会情報学研究科学年暦(2023年07月19日版)
- 2023(令和5)年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・1.4MB)
- 令和4年度社会情報学研究科時間割
- 令和4年度社会情報学研究科学年暦
- 令和4年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・0.6MB)
- 令和3年度社会情報学研究科時間割
- 令和3年度社会情報学研究科学年暦
- 令和3年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・0.7MB)
- 令和2年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・10MB)
- 平成31年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・14MB)
- 平成30年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・13MB)
- 平成29年度社会情報学研究科履修手引(Web掲載用簡易版・13MB)