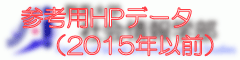大野富彦 (おおの・とみひこ)准教授

OHNO, Tomihiko
- 出身地: 東京都
- 最終学歴/学位: 中央大学大学院総合政策研究科総合政策専攻博士後期課程修了/博士(総合政策)中央大学
- 研究室: 社会情報学部棟606
- 所属学会: 日本経営学会,組織学会,経営情報学会,日本情報経営学会,日本ホスピタリティ・マネジメント学会,国際戦略経営研究学会
- 専門分野: 経営学
- 担当科目: 経営学Ⅰ・Ⅱ,コーポレート・ファイナンス
現在の研究テーマ
- 価値創造のための組織間および組織・顧客間の協働に関する研究
- 市場情報の獲得・蓄積・活用に関する研究
- 企業家の知識の成長に関する理論的・実践的研究
代表的な研究業績
専攻分野・研究内容紹介
経営学とはどんな学問か
私の専門は経営学です。経営学では,主に企業について研究します。といっても ??? だと思いますので,携帯電話を例にとって説明しましょう。
携帯電話でメールしたり写真を撮ったりすることがあると思います。携帯電話を製造・販売している企業は複数あり,皆さんはそのなかから自分好みの企業と機種を選んで購入しているはずです。これを企業の側からみると,「どうすれば消費者に自社製品を選んでもらえるか」,「どうすればライバル社に勝てるか」,「製品を効率的につくるにはどうすればいいか」等,経営上の様々な課題を見つけ解決しようとします。経営学とは(とても乱暴な整理ですが)こうした経営上の課題解決に役立つ考え方を提供する学問です。
学問として原理を探究する
私は,経営学に魅かれて学者になったわけですが,経歴は少し変わっています。大学時代は法律を専攻し,卒業後は銀行系のシンクタンクに就職しました。まさか自分が学者になるとは思っていませんでした。働いているうちに経営に興味を持ち(その時はまだ学問としての経営学ではありません),また,独立したいという身勝手な思いもあり,会社を辞めてコンサルティング事業を始めました。
この頃から学問としての経営学を意識し出します。コンサルティング事業では,多くの,そして様々な業種の企業や団体と仕事をさせてもらいました。コンサルタントとして仕事をしていくなかで,上手く説明はできないけど違和感を持ち始めます。企業人は本当に自分で考え考え抜いて意思決定しているのだろうか? 経営学に出てくる言葉を適当? に使ってそれらしい行動をしているつもりなのではないか? といったものです。もっと原理的なことをもとにした思考訓練が企業人や学生には必要なのではないかといった,これも身勝手な思い(その時は勘違いだったのかもしれません)を持って学者を志し,大学院に入り直しました。
2008年に学位をとった後,新潟のある私立大学にお世話になり,2011年10月に群馬大学に移ってきました。以上のようにちょっと変わった経歴で,また,学者としてのスタートも遅いのですが,原理的な内容にこだわることは決して勘違いではなかったと,今は思っています。
生の声を聞き,現場を見る
さて,研究に話を移します。私は,企業が価値を創造し成長していくプロセスに関心を持っています。もう少し言うと,どのような価値創造のあり方があるかといったものです。ここ数年は,市場情報を経営に役立てて価値創造につなげる上で,特に,「お客様相談室」の重要性に着目して事例研究を行なってきました。「お客様相談室」には毎日多くの声が寄せられます。それらを組織としてどのように活用していけば価値創造につながるか,あるいは,活用する際の課題は何かなどを,企業へのインタビューを通じて研究してきました。なお,インタビューという手法について,経営学は実践的な学問なので,生の声を聞いたり現場を見たりすることが大事になります。今後も,現場に足しげく通うつもりです。
原理をもとにした思考訓練
最後に,教育に対する考え方について述べます。原理的なことをもとにした思考訓練は譲れませんので,講義では,経営学の諸理論をまずおさえ,知識の引き出しを増やします。そして,ゼミでは,企業等の活動を,理論を応用して分析し自分の考えを持つことを重視しています。こうした取り組みが,社会に出てからの意思決定や行動に役立つと考え,それが企業の成長そして日本の成長へとつながると信じています。