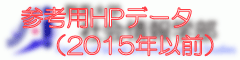末松美知子 (すえまつ・みちこ)教授

SUEMATSU, Michiko
- 出身地:東京都
- 最終学歴/学位:東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程/修士(英文学)
- 研究室:教養教育棟GC206
- 所属学会: 日本英文学会、 日本シェイクスピア協会 、日本演劇学会 、ルネッサンス研究所
- 専門分野: 英米演劇、比較演劇史
- 担当科目:舞台表象論、メディア・イングリッシュ
- 個人ページ: http://www.si.gunma-u.ac.jp/~sue/index.htm
現在の研究テーマ
- 演劇を含む舞台表象の社会における役割の研究
- 日英のシェイクスピア上演の比較研究
- 文化交流における芸術の可能性についての研究
代表的な研究業績
- 「シェイクスピア・アラカルト」高田康成ほか編『シェイクスピアへの架け橋』, 東京大学出版会, 1998, pp. 257-290.
- "Innovation and Continuity: two decades of Deguchi Norio's Shakespeare Theatre Company", Carruthers,I., Gillies, J. and Minami, R. (eds.), Performing Shakespeare in Japan, Cambridge University Press, 2001, pp. 101-111.
- "Import/export: Japanizing Shakespeare", Kennedy, D., Yong, L. L.(eds.), Shakespeare in Asia: Contemporary Performance, Cambridge University Press, 2009.
専攻分野・研究内容紹介
社会情報学部では主に「舞台表象論」と「メディア・イングリッシュ」を担当しています。舞台表象論とは聞きなれない言葉かもしれません。これは、舞台で上演される演劇や芸能、パフォーマンスなどを、それ自体で独立・完成したものとして捉えるのではなく、社会や文化における生成・伝達・受容の関係構造から解き明かそうという比較的新しい考え方です。もともと英文学を志していた私がなぜ今このような科目を社会情報学部で教えることとなったのかご説明しましょう。
演劇への関心
大学の英文学科で英米演劇を学ぼうと思ったのは自然な成り行きでした。思えば5歳にしてすでに英語劇に出演していました。個人的なことですが、学生であった戦争中に英語を勉強できなかった母が自分の外国への憧れを娘に託そうとしたのか、ほぼ強制的に幼いころから私を英語塾に通わせたのです。英語アレルギーを起こすこともなくその後も従順に英語を学び続けた私がいよいよ英語劇にのめりこんだのは中学時代でした。これもめぐり合わせなのでしょう。大学を卒業したばかりの演劇好きの先生が英語の授業の担当となり、授業で学生にちょっとした劇を演じさせたのです。そこで教えを受けた物好きが集まって毎年文化祭での英語劇公演という運びとなり、シェイクスピア劇の現代版なども上演しました。
中学や高校時代に学芸会の公演に出演したり裏方として活躍された方も多いと 思います。集団で何もないところから一つの舞台を作り上げ、多くの観客の前で披露し、最後に盛大な拍手を受ける -- この達成感は大変なものです。役者は三日やったらやめられないとはよく言ったものです。というわけで、大学でも英語劇のサークルに所属し夢を追い続けました。
研究への扉
英米演劇を本格的に研究したいと考え始めたのは、在学中の夏休みに出かけたイギリス語学研修中のことでした。週末にシェイクスピアの生誕地ストラトフォード・アポン・エイヴォンへ観劇に出かけた際のことです。舞台では『ヘンリー五世』という聞いたこともないシェイクスピアの歴史劇が上演されていました。3 階席からはるかに遠い舞台を眺めているうちに、ほとんどの友人は眠ってしまいました。英語も劇の筋もほとんどわからないのですから当然です。しかしわからないながらも私はせりふの力強さに圧倒されました。陰影のある美しい響きとうねるようなリズムに背筋がぞくぞくしたことを今でもよく覚えています。この時私は書かれた文字を読むこととせりふとして聞くことが全く別の体験であることを理解しました。英語という言語、あるいは、シェイクスピアの詩が人間の声を通して語られ立体化される美しさが私を魅了し圧倒したのです。
その時以来シェイクスピアという劇作家の作品を読み舞台を観続け、その魅力の解明に努めています。例えば、もう何十回となく『ハムレット』を舞台で観てきましたが、飽きることはありません。当然ですが一つとして同じ舞台は無いからです。人物やせりふに国や時代に即した解釈が加えられ、そのつど新しい作品に生まれ変わります。逆に言うと、解釈の余地が大きい -- これこそシェイクスピアが400年を経た今も上演され続ける理由なのです。
舞台表象論へ
社会情報学部で研究するようになってからは、シェイクスピアを文学的に読み解くだけでなく身体メディアという新たな視点から見直しています。演劇は身体というメディアを用いた表現・表象ですが、現代社会においてどのような意味や意義を持つのでしょうか。身体は人間にとって最も基本的なメディアです。コンピューター、携帯、書物や言葉がなくとも身体による表現やコミュニケーションは可能です。その人間の身体なくして演劇はありえません。基本である身体が、せりふ、音楽などの舞台上の諸要素とどのような関係を持ちどのようなメッセージを伝えるのかを分析しながら、身体というメディアや舞台表象の可能性についてこれからも考えていきたいと思っています。