Pages (HP Contents)

所属

研究室の場所

荒牧キャンパス (アクセス)
10号館 4階 408号室
連絡先

iwai@gunma-u.ac.jp
(@を半角にして下さい。)
※ 本研究室の研究生等を希望される場合は,まずゼミ,研究活動,発表の各ページをよく確認して下さい。中国からのご連絡の場合はこちらもご注意下さい。
Links

〔教員業務用〕
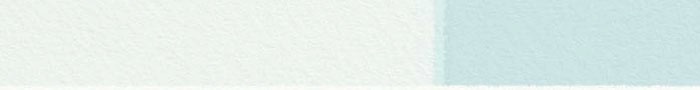

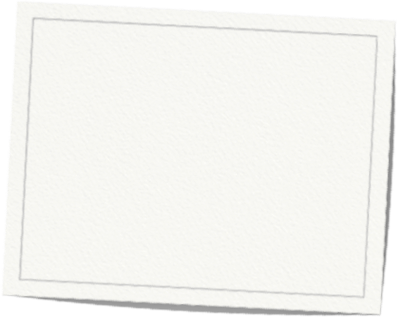
情報工学と社会学を背景に、主に意思決定支援システムの研究を行っています。匿名コミュニケーション、社会的選択理論に関連した支援法などが中心です。
(学生の方に)
|
本研究室は,群馬大学情報学部の意思決定支援研究室です。所属上の理由から,担当教員は長く「社会情報学」領域に貢献する意思決定支援を考えてきました。
「社会情報学」とは何でしょうか。「社会情報学」の呼び名は「社会の情報化」とともに生まれ,学会活動としてもすでに一定の経緯があります。また,人文科学・社会科学・情報科学の複合領域と言われますが,その定義の詳細についてはまだ議論が終わっていません。
学問が独自の名前を掲げる際は,独自性の根拠がなくてはなりません。諸学問に深く関連しても,どこかに独自の部分が残るのが通常です。「社会情報学」に,純粋な工学でない,経済学でもない,社会学等とも異なる部分があるとすれば,何でしょうか。ここでは,多くの学生の方が気になると思われますので,まず工学的な情報処理学との違いを意識してまとめたいと思います。なお,一般に数学,物理学,農学,医学などの学問も,しばしば研究者によって定義が変わります。そこで,これも一教員の考え方に過ぎませんが,本研究室での社会情報学の考え方を以下にまとめたいと思います。「社会の情報化」をどう捉えるかという点にも関連します。
社会情報学の独自性は,恐らく,近年企業や自治体が多くの社会的説明責任を意識している点や,広告や広報の目的で日常的に情報発信に努めている点に注意するとわかりやすいかと思います。大学教員がHP管理や高校訪問に時間を割いている例も参考になる。多くの個人が疲弊を感じつつSNS等の発信を続けている状況も興味深い。いわば「誰もが誰もにプレゼンテーションする時代」が到来しつつあり,ここに情報機器の普及とは別の「社会の情報化」の本質があるかと思います。
社会情報学の育成する職業者像は,どのようなものでしょう?例えば,メディア会見を開く企業や自治体の代表者を考えてみましょう。カメラと対時する代表者自身は,当面の目標ではありません(結果的に目標としてもよいのですが,それは法学,経営学,経済学など,どの分野も目標とするので,フェアでありません)。ですが,このときカメラに映らない別の組織側スタッフ,この会見の設定者はひとつの目標像としてよいと思います。その人は,社会に流れる多様な情報を独自の観点から統計分析し,組織の主脳陣にこの会見の必要性を伝え,メディア関係者を集めた人物です。会見後には実際の効果を追尾し,自身の権限の範囲でSNS上の追加発信等も行います。その職務の遂行には組織に関わる諸学の他,電子メディア技術を含め,メディアの知識も必要でしょう。
この職業者像は,もちろん新しいタイプのものです。例えば,地域の古い酒造メーカーであれば,歴史的に元は組織全員が酒造りの職人だったでしょう。しかし,貨幣経済が進展すると会計担当が,法務が複雑になると法務担当が組織に加わる展開となります。そして,情報の受発信がこれほどに複雑な様相を呈する今日では,新たに情報の専門家が求められる状況にあるのではないでしょうか。例えば,大学でも教員にHP管理や高校訪問を控えさせ,専門の職員を採用する場合があります。社会情報学の人材育成は,こうした需要に対応しつつあるように思われないでしょうか。
社会情報学には,独自の学問的な価値があると本研究室教員は思います。本研究室自体は,テーマ的に必ずしもその中心でありませんが,既存の様々な学問が関連する新領域ですから,相応に何らかの貢献ができるものと期待しています。
| 経歴 |
| 1988.4 | 東京工業大学工学部第5類入学 |
| 1989.4 | 東京工業大学工学部情報工学科所属 |
| 1992.3 | 東京工業大学工学部情報工学科卒業 |
| 1992.4 | 東京工業大学大学院理工学研究科 情報工学専攻修士課程入学 |
| 1993.3 | 東京工業大学大学院理工学研究科 情報工学専攻修士課程休学 |
| 1993.4 | 中国清華大学中国語言文学系留学 |
| 1994.4 | 東京工業大学大学院理工学研究科 情報工学専攻修士課程復学 |
| 1995.3 | 東京工業大学大学院理工学研究科 情報工学専攻修士課程修了 |
| 1995.4 | 東京工業大学大学院理工学研究科 社会工学専攻博士課程進学 |
| 1996.3 | 東京工業大学大学院理工学研究科 社会工学専攻博士課程中退 (指導教員の異動が生じ,行動を共にするため一旦退学して再入学。) |
| 1996.4 | 東京工業大学大学院社会理工学研究科 価値システム専攻博士課程入学 |
| 1997.6 | 東京工業大学大学院社会理工学研究科 価値システム専攻博士課程中退 |
| 1997.7 | 東京工業大学大学院社会理工学研究科 価値システム専攻社会数理講座 助手 |
| 1998.11 | 弘前大学 人文学部 情報行動講座 講師 |
| 2001.1 | 弘前大学 人文学部 情報行動講座 助教授 |
| 2002.3 | 博士(学術),東京工業大学 |
| 2002.4 | 群馬大学 社会情報学部 助教授 |
| 2006.4 | 群馬大学 社会情報学部 情報行動学科 助教授 |
| 2007.4 | 群馬大学 社会情報学部 情報行動学科 准教授 |
| 2016.4 | 群馬大学 社会情報学部 社会情報学科 准教授 |
| 2017.4 | 群馬大学 社会情報学部 社会情報学科 教授 |
| 2021.4 | 群馬大学 情報学部 情報学科 教授 (現在まで) |
| 所属学会 |
| 1 | 社会情報学会(SSI) 会員,理事,評議員 |
| 1 | 情報処理学会 会員 | 1 | 電子情報通信学会 会員 |
| 1 | 日本ソフトウェア科学会 会員 |
| 1 | 日本社会学会 会員 |
| 1 | 数理社会学会 会員 |
| 1 | American Sociological Association Associate Member |
| 1 | Human Development & Capability Association Member 他 |

教員の背景など