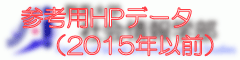情報社会科学科 経済
社会で活かせる専門性を磨く
経済科目群は,社会政策(労働経済論),経済政策(地域経済論),経済理論(ミクロ・マクロ),計量経済学(経済統計)といった4つの領域で構成されます。
カリキュラムは,基礎的な科目から実践的・応用的な科目群へと年次を追って配置されています。
1年前期では「現代経済入門」において,経済の基礎を身に付けることで現代経済の大枠を理解します。1年後期から2年前期にかけて,ミクロ・マクロ経済学や,経済量を取り扱う経済統計を学ぶことにより,経済理論の概要を学びます。同時に応用科目として,経済政策,地域経済論,労働経済論,財政学などで日本と欧米の経済の違いを学び,内容的にも地理的にも視野を広げます。
2年後期以後,情報経済分析,計量経済分析I・IIで経済学を実践的に扱うとともに,日本経済分析,社会政策などにより現代経済の構造的変化と政策課題の勉強をします。
最後に,経済科目群との境界領域である経営,環境,社会・行政,法律など諸科目を並行して履修し,現代(情報)社会の諸課題の中から自ら選択した課題の解決を目指して,卒業論文の作成に向かいます。この過程でみなさんは,社会情報学士としての専門性に磨きをかけ,獲得した専門知識を社会で活かしていくことになります。
科目紹介
一部の科目をご紹介します。
ミクロ経済学
ミクロ経済学の入門レベルの講義です。ミクロ経済学は,市場経済のメカニズムを個別の市場や主体の行動から説明しようとする方法です。内容は,比較優位と分業,需要・供給曲線,市場均衡の安定性,弾力性,余剰分析,消費者行動の理論,生産者行動の理論などです。
マクロ経済学
マクロ経済学の入門レベルの講義です。マクロ経済学は,市場経済のメカニズムを集計量を用いて説明する方法です。内容は,国民経済計算,ケインズと古典派,45度線モデル,IS-LMモデル,AD-ASモデル,貨幣と金融,インフレーションと失業などです。
金融論
市場・制度・金融機関からなる国際的な資金の融通・決済システムである国際通貨体制について,その変遷(金本位・金ドル本位・管理通貨)を固定為替から変動為替を通じて講義し,それらの問題を考察します。理論と実際の両面により検証します。