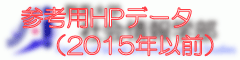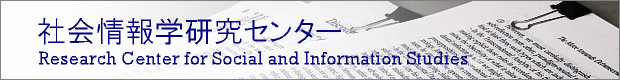
研究活動の要旨(2003年度)
社会情報基礎講座
環境科学第3研究室
[学会機関誌等への投稿]著者名:三上紘一
題名:初年次の少人数教育(半期)における動物実験について
掲載誌名:平成13年度文部省教養教育改善特別事業「大学初年次における体験型の自然科学系授業方法・カリキュラムの確立」報告書(代表 石川真一)、群馬大学教育研究センター基礎(自然系)専門委員会
発行年月日:2002年3月
頁:57〜67
要旨:自然環境教育における教材の活用方法の検討、および初年次の少人数教育における動物実験に関する授業方法の実践および受講生へのアンケートの結果を解析し、回数が少なくても実験実習は効果的な教育であることを示した。
著者名:三上紘一
題名:アフリカツメガエルオス幼生のメスへの性転換を指標とした内分泌撹乱化学物質検出に関するスクリーニング試験法開発の試み — エストラジオールを用いて — (仮題)
掲載誌名:環境省請負事業平成14年度「内分泌撹乱作用に関する両生類のスクリーニング・試験法開発」報告書
発行年月日:2003年9月発行予定
要旨:オスしか生まれない系統のアフリカツメガエルの幼生(オタマジャクシ)を用いて、内分泌撹乱化学物質にさらされた時、性転換が起こってメス化するかどうかを指標としてスクリーニングする方法の開発を目指して実験を行った。実験条件は、OECDの両生類部会で押し進めることになったXEMA法(Xenopus Metamorphosis Assay)を用い、合成女性ホルモンのエストラジオールを標準物質として、飼育容器に所定の濃度を添加し、その中で変態完了まで飼育を継続し、性転換の有無を調べた。その結果、1〜4nMの濃度でも十分にこのバイオアッセイ系で性転換が調べられることを報告した。実験回数が少ないので、今後、繰り返しの実験を通じて、確実なものとすることを報告した。
[その他]
著者名:三上紘一
題名:日常生活と環境問題一庶民としての雑感
掲載誌名:環境・安全広報
巻数:8
発行年月日:2002年3月
頁:6〜8
要旨:今日、色々の環境問題が取りざたされており、環境への配慮をしなければとの行動が少しづつ広まりつつあるが、一人の庶民として自分の身の回りを見たとき、まだ、十分でない状況が、アナウンスの面、販売の仕方、その後の処理の仕方等に多々見られることから、環境問題を意識しなくても環境に配慮した生活が自然に出来るような体制作りが急がれることを指摘した。
著者名:三上紘一
題名:大学の環境問題解決も民営化(民間委託)で良いのか?
掲載誌名:環境・安全広報
巻数:9
発行年月日:2003年3月
頁:5〜7
要旨:実験動物の焼却処理が、既存の大学内の処理施設では「ダイオキシン」の排出基準に適合しないため、民間委託をしなければならないとの話を動物実験施設から聞き、大学で行われている実験の特殊性(遺伝子組み替え動物を扱っているなど)と、処理に関して、様々なノウハウを持っていること、また、その開発をしなければならない立場にある大学が安易に外部委託をしてしまって良いのかという問題提起をした。
[学会等での発表、講演]
発表者名:三上紘一
題名:生命の科学
学会名(講演会名):新潟大学理学部の総合科目(理学部生全学年対象)
発表年月日:2003年8月11日〜13日
開催場所:新潟大学理学部
要旨:多細胞生物では、単に細胞が多数集まっているのではなく、細胞どうしがお互いに相手を求め、あるいは認識しあい、情報を交換する事によって、多細胞としての役割を果たしており、まったく、人間社会と同じである事を、細胞を培養する事によってしか得られない事実を示しながら、生命が如何にの神秘なものであるかを解説した。
外国語第2研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:福島光義
題名:Bleak HouseにおけるBucket警部の情報収集
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10
発行年月日:2003年3月31日
頁:1〜13
要旨:19世紀に、社会を理解する事の可能性への懐疑や不信が増大し、結果として、知る事の出来る関係と、知る事の出来ない社会との間に亀裂が生じている。Charles Dickensは後期の小説Bleak House(1852-53)において、共同社会認識の危機に対して重要な反応を示している。Dickensはロンドンの警察の集合的な力と情報収集力を描き、Bucketという人物を通じて社会についての新しい形の認識を表明している。Bucketは特別に注目を引く人差指を与えられており、それはグロテスクな描かれ方をしている。本論文は、Bucketの人差指によって代弁される社会共同体の構造を分析し、又捜査中におけるBucketの独特の情報収集方法を探り、更に、公私両面におけるBucketの他の人達への親切な態度や人間味について分析している。
「情報決定」第1研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:富山慶典,森 美有紀,熊田禎宣
題名:交流の6段階モデルによる高齢者の社会参画を促進する要因分析 — 「ミレニアム・プロジェクト」・桐生多世代交流実験を事例として —
掲載誌名:日本地域学会第39回(2002年)年次大会学術発表論文集
発行年月日:2002年10月6日
頁:349-356
要旨:日本の高齢者は高い就業意欲を持っている.しかし,仕事を除いた社会活動にでさえ高齢者が活発に参加できる場はほとんど存在していない.彼らの住む地域で多世代交流を実行することがこのような場を作り出し,その場が高齢者の就業の機会を生み出すのではなかろうか.本研究の目的は,一般的な交流の6段階モデルを構築し,ミレニアム・プロジェクトの一事業である桐生の多世代交流実験にそのモデルを適用し,高齢者の社会参画を促進する要因を分析することにある.分析の結果は,成功した多世代交流が「地域ネットワーク」,「地域エデュケーション」,「地域インフォメーション」という3つの要因をもっていることを示している.最後に,これらの要因の一般性が検討される.
[学会等での発表]
発表者名:富山慶典
題名:意思決定と情報技術 — 電子民主主義に関する最近の研究動向と今後の課題 —
学会名(講演会名):専門訴訟事件等の特殊事件のための研究会
発表年月日:2002年11月1日
開催場所:前橋地方裁判所大会議室(本館5階)
要旨:裁判を意思決定の一つと捉えたときの問題点(裁判員制度の意味するもの等)、電子投票制度の意義(新見市の例等)、高齢化社会等から見た電子民主主義等について講演した.
[学会等での発表]
発表者名:富山慶典
題名:環境政策を選ぶための情報の集約と開示はどうあるべきか? 〜不確実性のもとでの合意形成手法の開発を念頭において〜
学会名(講演会名):日本社会情報学会第88回研究会(テーマ:環境問題への社会情報学的パースペクティブ)
発表年月日:2003年6月4日
開催場所:電気通信大学大学院情報システム学研究科棟2F215(中会議室)
要旨:既発表論文(富山慶典.2002.不確実性のもとでの集合的意思決定ム私的情報の集約と公的情報の開示ム.遠藤 薫(編著)『環境としての情報空間−社会的コミュニケーション・プロセスの理論とデザイン』.169-193.)の内容を踏まえて,不確実性のもとでの合意形成手法の開発を念頭におきながら,環境政策の選択問題への応用可能性を検討した.
[学会等での発表]
発表者名:富山慶典
題名:不確実性のもとでの集団意思決定 — 電子民主主義のための基礎理論の構築をめざして —
学会名(講演会名):東京工業大学・朝日カルチャーセンター連携公開講座『社会情報学とは何か』
発表年月日:2003年8月9日
開催場所:東京工業大学大岡山キャンパス9号館707教室
要旨:既発表論文(富山慶典.2002.不確実性のもとでの集合的意思決定ム私的情報の集約と公的情報の開示ム.遠藤 薫(編著)『環境としての情報空間 — 社会的コミュニケーション・プロセスの理論とデザイン』.169-193.)の内容を踏まえて,それが電子民主主義のための基礎理論としてどのように位置づけることが可能であるかを検討した.
[学会等での発表]
発表者名:富山慶典
題名:「選好集約論」の探求から「判断形成論」の探求へ — 民主的社会のための新たな集合的意思決定論の構築をめざして —
学会名(講演会名):第36回数理社会学会大会研究報告要旨集,30-33.
発表年月日:2003年9月20日
開催場所: 慶応義塾大学三田キャンパス
要旨:民主的社会には,“選好”にもとづく集合的意思決定問題と“判断”にもとづく集合的意思決定問題の2つがある.これまでの集合的意思決定の研究は選好集約論の探求に偏りすぎていた.判断形成論の探求をすすめる必要がある.そうだとすれば,この探求には現代の社会にとってどのような意義があるのか,民主的決定の隣接領域における最近の研究動向とはいかなる関連性をみてとれるのか.本研究の目的は,古代ギリシャから現代までの集合的意思決定研究の歴史を振り返ることにより,これらの問いにたいする暫定的な答えを得ようとすることにある.
[学会機関誌等への投稿]
著者名:小竹裕人,岩井 淳,富山慶典
題名:地方自治体の意思決定支援と情報・討議・決定
掲載誌名:日本社会情報学会(JASI)第18回全国大会研究発表論文集
巻数:第18巻
号数:第1号
発行年月日:2003年9月1日
頁:227-232
要旨:Support for residents to make decisions for their autonomy is one of the key domains with informatization of a society. The task is related with different arguments of empowerment of local government, development of DSS and logics in social choice theory. This paper reviews the three contexts with respect of a model of ‘information, deliberation and decision’presented in a research of electronic democracy (Tomiyama(2002)). As a conclusion, this paper illustrates how a supporting system can be feasible while there are conflicts among the basic notions in the original arguments.
[学会等での発表]
発表者名:富山慶典
題名:E-デモクラシーとP2P技術 〜意思決定科学からのアプローチ〜
学会名(講演会名):電子情報通信学会・コミュニティ活性化研究会(テーマ:まちづくりの現場が求めるネットワーク−地域コミュニティ活動と次世代技術の融合−)
発表年月日:2003年10月18日
開催場所:桐生地域地場産業振興センター
要旨:決定・討議・情報を基本的な3要素とするE-デモクラシーの理論的枠組(富山慶典.2002.電子民主主義における決定と討議と情報についてム意思決定科学の立場からの研究課題ム.日本社会情報学会(旧日本都市情報学会)第17回全国大会研究発表論文集,45-50.)を踏まえて,E-デモクラシーのプラットフォームとしてのP2P技術の応用可能性を検討した.
外国語第3研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:Michiko Suematsu
題名:The Cherry Tree and the Lotus: Ninagawa Yukio's Two Macbeths
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10
号数:
発行年月日:2003年3月31日
頁:15〜23
要旨:1980年以来、蜷川幸雄は日本を代表するシェイクスピア作品の演出家として世界的な成果をあげてきた。中でも、1980年の『マクベス』は、独特な蜷川スタイルを確立し、初めて海外公演を成功させた作品として、注目に値する。2001年、蜷川は新たな演出で再び『マクベス』上演を試みた。本論では、この2作品を詳細に分析し、両作品の共通点、相違点を明らかにした上で、世界的な演劇状況における、蜷川を含めた日本のシェイクスピアの可能性を検討した。
[学会等での発表]
発表者名:末松美知子
題名:日本から世界へ — シェイクスピアの海外公演
学会名(講演会名):2003年度日本演劇学会全国大会
発表年月日:2003年5月24日
開催場所:関西外国語大学
要旨:海外からの受容に終始してきた日本でのシェイクスピア公演も、ここ20年、日本から海外への発信が目立ってきた。本発表では、日本の代表的な演出家となった蜷川幸雄のシェイクスピア海外公演『ニナガワ・マクべス』(1985)、『リア王』(1999)、『マクベス』(2002)、『ぺリクリーズ』(2003)について、内外の評価の温度差も含めて、その成果と意義を検証した。さらに、蜷川の海外公演を手がかりに、日本のシェイクスピアとはあくまで「日本風な」シェイクスピアに過ぎないのか、あるいは、異なる文化の融合による新しい「読み」を積極的に提供し、今までに無いシェイクスピア上演の可能性を提示しえているのか等、日本のシェイクスピア上演の可能性や意義を検討した。
[学会等での発表]
発表者名:末松美知子
題名:『十二夜』の蘇生 — ミドル・テンプル・ホールからグローブ座へ
学会名(講演会名):第42回シェイクスピア学会
発表年月日:2003年10月11日
開催場所:金沢大学
要旨:記録に残る『十二夜』の初演、1602年2月2日のミドル・テンプル・ホールにおける上演から400年を経た2002年、ロンドンのグローブ座カンパニーは、このホールで、「最も歴史的に忠実な」『十二夜』を記念公演として上演した。この『十二夜』は、当時の室内劇場での上演を検証できる絶好の機会となり、演劇的な実験としては貴重で発見も多かったが、残念ながら上演としては、不満足な結果であった。
2002年5月、グローブ座夏のシーズンが開幕し、ミドル・テンプル・ホールの『十二夜』はこの劇場で再演され、活力にあふれた作品として蘇った。本発表では、いかにしてこの『十二夜』が「蘇生」したのか、グローブ座という上演空間とシェイクスピアの劇作法の関係を再考しつつ検証した。
環境科学研究室
[著書]
著者名:小田信治、小松裕幸・著、石川真一(監修)
題名:エコロジカルデザイン:アドバンテスト群馬R&Dセンター敷地内ビオトープ.「建築設計資料集成:地域・都市Ⅰ — プロジェクト編」日本建築学会・編
担当頁:178-179
発行年月日:2003年9月
発行元:丸善
要旨:全国の大学工学部建設工学科で教科書として用いられる「建築設計資料集成」がおよそ20年ぶりに改訂され、その中でアドバンテスト群馬R&Dセンター敷地内ビオトープの建設・維持管理手法を概説した。近年世界的に自然再生事業として行われれるようになったビオトープであるが、その建設・維持管理は当該地の多様な自然環境に合わせて行う必要がある。本稿では、日本最大のビオトープの成立過程を、当該地の立地条件とともに概説した。
[学会機関誌等への投稿]
著者名:石川真一、高橋和雄、吉井弘昭
題名:利根川中流域における外来植物オオブタクサ(Ambrosia trifida)の分布状況と発芽・生長特性
掲載誌名:保全生態学研究(日本生態学会第二和文誌)
巻数:8
頁:11-24
発行年月日:2003年8月
要旨:花粉症や生態系破壊の原因とされる外来植物オオブタクサ(Ambrosia trifida)の、群馬県内利根川中流域における分布状況を調査した結果、県南端に位置する明和町から、県北端の水上町(源流から約30km下流)の範囲において、大きな個体群が30地点で確認され、このうち最大のものは約687万個体からなり、年間約17億の種子を生産していると推定された。またこの30地点はすべて工事現場や採石場周辺などの、人為的撹乱地であった。また水上町の個体群と群馬県南部の伊勢崎市の個体群において残存率調査と生長解析を行った結果、オオブタクサは北の低温環境下においても南部と同等かそれ以上の相対生長速度を有しているが、エマージェンス時期が遅くて生育期間が短いため、個体乾燥重量は小さくなった。しかし水上町では、伊勢崎市に比べて個体乾燥重量あたりの種子生産数と残存率および個体群密度が高いため、単位面積あたりでは伊勢崎市より多くの種子を生産していた。これらの結果から、オオブタクサが今後も低温環境下において勢力を拡大する危険性があるとことが示唆され、拡大防止の一方策として、河川周辺における人為的撹乱の低減と、種子を含む土壌が工事車両によって移動することを防止する必要性が提言された。
[その他著作]
(評論)
著者名:石川真一
題名:温暖化はもはや防げない? — 追われる生物、迷走する人類 —
掲載誌名:群馬評論
巻数:94
頁:62-67
要旨:地球温暖化の原因、メカニズムを概説し、またその将来における自然・生物・人類に対する影響予測に関する近年の研究成果をとりまとめた。これらをもとにして、温暖化防止に根元的に必要な5条件を提唱した。すなわち、人口抑制と貧困の改善、化石燃料の廃止と代替エネルギーの利用、長期的研究のための基盤整備、およびこれらを阻害する政治・行政上の凋落の改善、である。
(報告書)
著者名:石川真一
題名:ビオトープの管理・育成に関する調査研究
発行年月日:2003年3月
要旨:2002年度ビオトープ基金による。近年、ビオトープと呼ばれる人工生態系を構築することによって、地域の自然を再生しようとする試みが産業界、教育界を中心に盛んになっている。しかし、その手法のほとんどは経験的で、トライ・アンド・エラーを繰り返し、成功にはほど遠い。そこで、このビオトープをを育成するための環境科学的調査研究を行った結果、次の2点が解明された。ビオトープ竣工後に起こる生物の侵入・定着パターンが、一般撹乱地におけるものとほぼ同様であることが明らかになった。2. 特に帰化植物と呼ばれる、地域生態系を破壊する恐れのある植物の侵入が顕著であるが、管理手法の改良により、少なくとも一年生帰化植物については抑制が可能であることが明らかになった。
著者名:石川真一、三上紘一、中田吉郎、他
題名:新学習指導要領と「新しい時代における教養教育の在り方について」答申に対応した自然科学系大学初年次教育の新教材・授業方法の確立
発行年月日:2003年3月
要旨:平成14年度群馬大学教育研究重点経費による。平成14年度より「新学習指導要領」が始まり、平成17年度にはこのもとで中等教育をうけた学生を本学でも受け入れることになる。新学習指導要領では必修内容が現行のものとくらべて1/3ほど少なくなる。このような中等教育を受けた学生の知的水準を、より高度化して専門教育に”橋わたし”するためには、初年次教育を全面的に見直し、いっそうの充実に務めなくてはならない。また、「新しい時代における教養教育の在り方について」答申では、授業科目を複数の教員で担当したり実験や実習を取り入れたりなど、カリキュラム改革や指導方法の改善により「感銘と感動を与え知的好奇心を喚起する授業」を生み出すことが要求されている。このためのカリキュラム改革の基盤となる諸学生実験環境の改善および教材の整備を行い、その実効性を検証した。
著者名:石川真一、三上紘一、中島照雄、西村淑子、杉山学、樋田勉、他
題名:環境政策策定支援システムの構築に係る学内共同研究
発行年月日:2003年3月
要旨:平成14年度群馬大学教育研究重点経費による。人類の存続・繁栄のカギは、さまざまなレベルにおける環境政策にある。特に地球環境問題の解決や地域環境の整備等に関しては、総合大学たる群馬大学は、政策立案の直接支援および政策立案者の養成の2つの面で、大いに貢献してゆく必要がある。
本プロジェクトでは、こうした貢献を行う学内横断的体制を確立することを目的として、以下の3つのサブプロジェクトを行った。〈1〉環境情報収集システムの構築 〈2〉環境法、環境税制の国際比較データベースの構築 〈3〉環境政策策定支援シミュレーションモデルの構築。
著者名:石川真一、三上紘一、今村元義、落合信高、下田博次
題名:下仁田町新教育産業用地域・環境教育資材の開発のための社会情報学的共同
発行年月日:2003年3月
要旨:平成14年度群馬大学教育研究重点経費(社会貢献重点経費)による。
群馬県下仁田町において近年発足した、新教育産業に用いられる地域・環境教育資材を開発・整備した。ここでいう地域・環境教育資材とは、当地で発足した町立自然学校、自然史館において教育を行う際に教材として用いる、地域の自然環境情報や人文社会学的特性およびこれらに関する社会情報学的知見のことである。具体的には、次の通りである.(1)下仁田町と周辺地域の地質・地下資源分布とそのデータベース(2)同地域の植生分布・植物生理活性とそのデータベース(3)同地域の気象・大気環境・土壌環境特性とそのデータベース(4)同地域の土地利用の歴史、産業盛衰の歴史とそのデータベース。
[学会等での発表]
発表者名:石川真一
題名:文理融合分野としての環境科学の近年の取り組み
学会名:日本社会情報学会第7会大会ワークショップ「持続可能な社会構築のための”環境”」
発表年月日:2002年11月17日
開催場所:群馬・群馬大学
要旨:文理融合分野としておよそ30年間行われてきた環境科学の近年の取り組み、特に持続可能な社会構築のための取り組みを概説し、また環境科学の基礎概念として主体−環境論、作用−反作用、学際性などについても概説した。
発表者名:石川真一、亀沢秀一
題名:平地雑木林と高地ブナ林におけるリター生成・分解速度の季節変化
学会名:日本生態学会第50回大会
発表年月日:2003年3月
開催場所:茨城・エポカルつくば国際会議場
2003年3月
要旨:IPCCの第三次報告書(2001)によると、21世紀中に大気中のCO2は最大で490〜1260ppm、地球の平均気温が1.4〜5.8℃上昇すると予測されている。一方、生態系でのCO2の収支バランスは、特に森林において未解明部分が多く、とりわけリター(落葉落枝)の生成・分解速度に関するデータが不足している。 そこで、立地と構成樹種の異なる二つの森林生態系において、リターの生産・分解速度および含水率・地温との相関について解析した。群馬大学構内雑木林においては、リター分解速度は夏期の6〜8月期にもっとも高く、0.004〜0.005g/g/dayとなっていた。秋期・冬期の9〜4月にはリターの分解速度は低下し、0.001〜0.003g/g/dayとなっていた。玉原高原ブナ林ではリターの分解速度は7〜10月に0.004〜0.005g/g/dayと、雑木林と同等の値となっていた。ところが冬期積雪期には0.001g/g/dayと非常に低い値となった。リター生成速度はブナ林で1427g/m2/yr、雑木林で55770g/m2/yrと大きな違いがあった。以上のことから、ブナ林においては、リター由来のCO2放出量は、雑木林に比べて非常に低く、その原因は、リター生成量が少ないこと、低温と積雪により分解速度が低下することであると考えられる。
発表者名:石川真一
題名:21世紀がなぜ「環境の世紀」と呼ばれるのか
学会名:社会情報学部総合科学シンポジウム「環境の世紀」における環境施策の展
発表年月日:2002年10月3日
開催場所:群馬・群馬大学
要旨:1992年の地球サミットから2002年の環境サミットに至るまで、世界の環境科学の取り組み状況、特に持続可能な社会構築のための取り組みを概説し、また環境科学の基礎概念として主体ー環境論、作用ー反作用、学際性などについても概説した。
発表者名:石川真一
題名:地球環境情報と温暖化対策
学会名:社会情報学部総合科学シンポジウム「環境の世紀」における環境施策の展
発表年月日:2002年10月3日
開催場所:群馬・群馬大学
要旨:IPCCレポート(2000)に基づく地球環境変化の最新予測・最新影響予測、および世界の地球環境情報の構築体制について概説した。また、二酸化炭素濃度増大と温暖化が樹木の生長と森林の炭素循環に及ぼす影響について、最新の実験・解析から得られた結果に基づいて論じた。
[社会的活動]
発表者名:石川真一
題名:農業と環境(文部科学省社会人キャリアアップ講座「元気の出るアグリ講座」)
開催年月日:2003年1月11日
開催場所:群馬・昭和村公民館
要旨:文部科学省・群馬県よりの依頼講演。今後の地球環境変化によって農業にどのようなインパクトがあるか、またそのメカニズムについて概説した。
開催者名:石川真一
題名:教養教育合宿実習「群馬県本白根山の自然環境の成り立ちと保全」
開催年月日:2003年7月5日〜6日
開催場所:群馬県草津町
要旨:群馬大学学生を対象とし、草津白根山の自然環境資源としての重要性や、周辺地域の産業がいかに自然環境資源をうまく利用して成り立っているかを体験する実習。
開催者名:石川真一
題名:ビオトープ育成のための環境科学的調査研究と講習
開催年月日:2003年4月〜月一回開催
開催場所:群馬県明和町
要旨:(株)アドバンテスト群馬R&Dセンター(群馬県明和町)内に竣工したビオトープを育成する環境科学的調査研究を行い、これに基づいて講習を行った。(株)アドバンテストビオトープ基金により助成を受けた。
外国語第4研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:井門 亮
題名:Incomplete Utterance and Relevance
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:第10巻
発行年月日:2003年3月31日
頁:25〜38
要旨:本論では、口語によくみられるincomplete utteranceの省略内容について、関連性理論での表意の強弱という観点から分析を行ない、incomplete utteranceのような文法的には不完全な文の場合、話者は非常に弱い表意しか伝えていないが、聞き手は、その発話自体と文脈とを手懸りに、関連性の原理に基づいて省略部分を表意の一部として復元するということを明らかにした。
[学会等での発表]
発表者名:井門 亮
題名:関連性理論からみた<類似性>に基づく表現:Likeと「よう」を中心に
学会名(講演会名):日本認知言語学会第4回全国大会
発表年月日:2003年9月14日
開催場所:明治学院大学
要旨:Andersen (1998, 2000, 2001) では、談話標識のlikeを、発話と思考のnon-identical resemblanceの関係を示す手続き的意味を持つ標識であると分析している。本発表では、likeに対応する「よう」「みたい」「ふう」といった様々な日本語表現も同様にnon-identical resemblanceを示すために用いられているか検討した。
社会・情報行動講座
地域社会史研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:落合延孝
題名:幕末を生きた地方役人の歴史体験と歴史意識−森村新蔵「享和以来新聞記」を読む
掲載誌名:九州史学
号数:136号
発行年月日:2003年11月
頁:1-11
要旨:「享和以来新聞記」を記録した森村新蔵が幕末維新期の重要な事件に遭遇し、どのような歴史体験を積み同時代をどのように認識したかを検討した。
[史料紹介]
著者名:落合延孝
題名:武州一揆の史料紹介−森村新蔵「享和以来新聞記」より−
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
号数:第10巻
発行年月日:2003年3月
頁:245-276
要旨:森村新蔵「享和以来新聞記」巻之九に記録された武州一揆に関する史料紹介を行い解説を付した。
[書評]
著者名:落合延孝
題名:須田努『「悪党』の一九世紀−民衆運動の変質と"近代移行期"
掲載誌名:日本歴史
号数:662号
発行年月日:2003年7月
頁:116-117
要旨:著書の紹介と著者の悪党論を批判的に論じた。
[学会等での講演]
発表者名:落合延孝
題名:長期古文書講座
学会名(講演会名):群馬県立文書館
発表年月日:2003年9月27日・10月4日・18日・25日・11月1日
開催場所:群馬県立文書館
要旨:上野国碓氷郡東上磯部村の萩原家文書を読みながら、江戸時代における村の自治のしくみを考察した。
[学会等での講演]
発表者名:落合延孝
題名:幕末維新期の情報と文化
学会名(講演会名):?魚の会
発表年月日:2003年11月16日
開催場所:群馬県立文書館
要旨:森村新蔵の「享和以来新聞記」を題材としながら、情報のネットワークと地方の文化について論じた。
外国文化第2研究室
[分担執筆]
執筆者名:荒木詳二 斉藤佑史
書名:ドイツ文法プレリュード
発行所名:郁文堂
発行年月日:2003年4月1日
分担執筆の頁:3課・4課・5課・6課・9課・10課
要旨:本書はドイツ語初級者用の文法教材である。
[社会的活動]
団体名:国際ロータリークラブ群馬支部
実施年月日:2002年8月11日
開催場所:前橋テルサ
要旨:国際奨学生希望者に独語の面接を実施した。
外国文化研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:小林 徹
題名:機械が造るモンスター — 『フランケンシュタイン』、映画、そして1930年代初頭 —
掲載誌名:IVY
巻数:第36巻
発行年月日:2003年10月31日
頁:1〜18
要旨:1818年にMary Shelleyが創作した人造人間の物語は、1931年、James Whale監督による映画化により、一挙に知名度が上がった。本稿では、この映画版Frankensteinをめぐり、フランケンシュタインの物語、1930年代初頭、そして映画という芸術形式の三項の関係性について、その作品とほぼ同時期に発表された、Walter Benjaminによる”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”を参照しつつ考察した。ホエールの作品は、当時既に顕在化していた、映画それ自体に関わる技術的必然と、資本主義体制下の大衆に関わる社会的必然に基づき成立していたである。
理論社会学研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:伊藤賢一
題名:社会秩序の正統性と安定性 — Habermasにおける法の概念
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10巻
発行年月日:2003年3月31日
頁:115〜129
要旨:Habermasにおける法の概念は80年代と90年代では様相を異にする。以前は両義的な役割を担っていた法は、今や、コミュニケーション権力を行政権力に転換するためのメディアという、より積極的な役割を果たすようになった。しかしこの理論的変化の意味は十分明らかにされておらず、本論はその解明を目指すものである。この変化の中心的な理由は、『事実性と妥当性』において望ましい社会の像が刷新されていることにある。それは、正統性と安定性という二つの要請を同時に充たす社会秩序の構想である。
[学会等での発表]
発表者名:伊藤賢一
題名:J. ハーバマスにおける国民国家の位置づけ
学会名(講演会名):第43回日本社会学史学会大会
発表年月日:2003年6月28日
開催場所:東北公益文科大学
要旨:本報告は、グローバリゼーションに関するHabermasの議論を参照しながら、国民国家概念の位置づけについて論じたものである。審議的政治という民主的プロセスにおいて不可欠の連帯を提供するものとして、ネーション概念に注目するものである。
政策・行政情報講座
立法学研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者:中村喜美郎
題名:大学統合について
掲載誌名:サンデージャーナル
号数:No.1045
発行年月日:2003年1月5日
頁:2〜4
要旨:群馬大学と埼玉大学との再編統合問題に関する経緯と問題点等について、ぐんま地域創造懇話会(代表幹事、本吉修二・天野譲)における報告を記録したもの。
[学会機関誌等への投稿]
著者:中村喜美郎
題名:大学改革と文理融合をめぐって
掲載誌名:融合
号数:No.16
発行年月日:2003年1月31日
頁:25〜27
要旨:昨今の大学改革論議の中で、文理融合の問題がクローズアップされてきている。これに関連した学部創設、学会研究大会でのテーマ、研究面における文理融合等について述べたもの。
民事法研究室
[著書]
著者名:前田泰
書名:人身賠償・補償研究 第5巻(日本交通法学会編)
発行所名 :判例タイムズ社
発行年月日:2002年12月
要旨:「精神障害者の関わる交通事故」の標題で、精神障害者が交通事故の加害者になった場合と被害者になった場合とに分けて、健常者の場合と異なる扱いを受ける場面を整理し、あるべき障害者の法的地位を論じた。判例タイムズ965号(1998年)に掲載した同名の論文を、その後の法改正に伴う加筆修正を加えて本書に収録した(281頁-304頁)。
[著書]
著者名:前田泰
書名:民法� 親族・相続法(伊藤進編)
発行所名 :北樹出版
発行年月日:2003年4月
要旨: 親族・相続法の全般にわたり、基本的な問題を体系的に整理し、簡明に要説する教科書の分担執筆である。「第1編 親族法」の「第2章 家事事件を処理するための手続き」、「第3章 親族とは」、および、「第4章 戸籍と氏」を担当した(23頁-39頁)。
[学会機関誌等への投稿]
著者名:前田泰
題名:判例にあらわれた高齢者の意思能力
掲載誌名:老年精神医学雑誌
巻数:13巻
号数:10号
発行年月日:2002年10月
頁:1151頁〜1157頁
要旨:財産取引に関する意思能力が争われた裁判例の中から、本人の年齢が60歳以上であるケースおよび痴呆等の脳障害に関するケースを収集し紹介・検討した結果、裁判所が、障害内容・程度から直接に意思能力の有無を判定しているのではなく、問題となる取引の効力を否定することにより障害者本人その他の利害関係人に生じる法的影響を考慮したうえで、意思能力の有無を判定することが多いという結論を得た。
[学会機関誌等への投稿]
著者名:前田泰
題名:能力判定の法的課題と展望
掲載誌名:実践成年後見
巻数:
号数:6号
発行年月日:2003年7月
頁:57頁〜68頁
要旨:掲載誌の特集「成年後見における能力判定」の一部として、成年後見法下の鑑定例、審判例、最高裁家庭局の示す典型例、および、名古屋家庭裁判所による補助診断書の調査結果を検討し、各成年後見を開始する基準につき、いわゆる生物学的要素を過度に重視していることを指摘し、心理学的要素を考慮すべきことを主張した。
政策過程論研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:伊藤修一郎
題名:景観まちづくり条例の展開と相互参照
掲載誌名:自治研究
巻数:第79巻
号数:第3号
発行年月日:2003年3月
頁:97−112
要旨:政策内容の変遷を把握する理論的枠組みを政策移転研究を手掛かりに提起し、1960年代から1980年代末までの景観条例に適用し、そこに盛り込まれた政策手段の変遷を追跡した。その結果、政策イノベーションは、少数の突出した先駆自治体に担われるのではなく、多くの自治体の相互作用の中から生み出されることが明らかになった。
著者名:伊藤修一郎
題名:群馬県内市町村景観条例制定過程における相互参照と情報の役割
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
号数:10号
発行年月日:2003年3月
頁:131−149
要旨:一連の担当部局ヒアリング調査に基づき、群馬県内市町村の景観条例制定過程を追跡した事例研究。自治体単体の政策過程を追う通常の事例研究ではなく、景観条例を制定した10市町村を追跡することで、各自治体の政治状況だけでなく、自治体相互のネットワークや情報交換が、条例制定を促す重要な要因であることを解明した。また、県と市町村の連合組織が、市町村の情報交換とリソースの提供に寄与したことも明らかにした。
著者名:伊藤修一郎
題名:まちづくりのモデルはどこか:共同通信社調査から読み解く自治体間の相互参照
掲載誌名:社会情報学研究
号数:7号
発行年月日:2003年5月
頁:1−12
要旨:全首長アンケートデータを分析して、まちづくり政策の策定に当たって、どの自治体がどの自治体をモデルとするのか(相互参照の様態)を探求した。その結果、相互参照の対象は時間と共に変化すること、近隣の自治体を参照するわけではないこと、同規模・同格の自治体を参照する傾向があること等が確認された。
著者名:伊藤修一郎
題名:自治体政策過程における相互参照経路を探る:景観条例のクラスター分析
掲載誌名:年報公共政策(公共政策学会年報)
号数:3号
発行年月日:2003年10月
要旨:政策は自治体間の模倣と改善によって進化するが、聴取調査やアンケートによってどこがどこを参照したかを特定することは極めて困難である。そこで、その方法論的課題を克服するために、クラスター分析を用いて政策の類似度を判定し、自治体間の参照経路を特定する方法を提唱した。更に、景観条例を事例としてこの方法を適用し、聴取調査によって特定された結果と矛盾しないことを確認した。
[分担執筆]
執筆者名:伊藤修一郎
題名:自治体政策過程のダイナミズム
編著者名:香川敏幸・小島朋之
書名:総合政策学の最先端(第4巻)
発行所名:慶應義塾大学出版会
発行年月日:2003年9月
要旨:自治体の政策イノベーションは単にひとつの自治体の創意で生み出されるのではなく、複数の自治体による模倣と改善の繰り返しの中から多様化と淘汰のプロセスを経て進化することを例証した。この推進力となるのが相互参照であることを示し、自治体改革の見取り図として、この行動を強化する方向を提案した。
[学会等での発表]
討論者名:伊藤修一郎
学会名:International Public Management Network 2003 Workshop
発表年月日:2003年9月
開催場所:モントレー、米国カリフォルニア州
要旨:IPMNで発行する学会誌International Public Management Journalの編集委員による研究集会の討論者を務めた。
[講演等]
講演者名:伊藤修一郎
講演題目:研究成果を政策にどう活かすか:自治体組織理論の視点
講演会名:政策研究フォーラム基調講演
発表年月日:2003年2月
開催場所:群馬県庁
要旨:自治体組織理論の視点の観点から、自主研究活動の活かし方、組織活性化のあり方を論じた。
講演者名:伊藤修一郎
講演題目:自主研の方法論
講演会名:市町村職員自主研究グループ認定式基調講演
発表年月日:2003年7月
開催場所:群馬県市町村振興協会
要旨:今後の自治体の進むべき方向とそれに即応した自主研究活動の進め方について論じた。
[その他]
聞き手:伊藤修一郎
題名:松沢成文神奈川県知事との対談
掲載誌名:三田評論10月号
発行年月日:2003年10月
行政法研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:西村淑子
題名:道路公害訴訟における差止請求
掲載誌名:法律のひろば
巻数:56
号数:6
発行年月日:2003年6月1日
頁:21〜27
要旨:道路の沿道住民が、道路の設置管理者である国等に対し、自動車排出ガスにより健康被害を被ったとして、損害賠償を求めるとともに、一定の数値を超える自動車排出ガスの排出差止めを求める訴訟を提起しており、裁判例のなかには、このような差止請求を認容するものも現れるようになった。
本稿は、道路公害訴訟における差止請求の適法性及び本案の当否について、判例及び学説を検討し、問題の所在を明らかにしたもの。
知的財産法研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:駒田泰土
題名:「判例研究 キューピー人形事件」
掲載誌名:著作権研究
号数:27号
発行年月日:2003年2月
頁:275〜286
要旨:東京高裁平成13年5月30日判決(判時1797号111頁)の評釈。
著者名:駒田泰土
題名:「インターネットを介した商標権侵害事件の裁判管轄 — 米国法の観点から — 」
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10巻
発行年月日:2003年3月31日
頁:231〜243
要旨:インターネットを介した商標権侵害事件の人的管轄権問題について、米国において生成しつつある判例法理を抽出し、論評したもの。
著者名:駒田泰土
題名:「ファイル共有ソフトを製造・頒布している者の著作権侵害責任を否定した米国カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所判決(2003年4月25日) Metro - Goldwyn - Mayer Studios, Inc., et al. v. Grokster, Ltd., et al. Jerry Lieber, et al. v. Consumer Empowerment BV a/k/a Fasttrack, et al.」
掲載誌名:Law & Technology
号数:21号
発行年月日:2003年10月1日
頁:134〜138
要旨:標記の判決の概要を紹介し、若干の論評を加えたもの。
[学会等での発表]
発表者名:駒田泰土
題名:「フェアユース的規定の可能性」
学会名(講演会名):「著作権の権利制限規定のあり方に関する調査研究委員会」
発表年月日:2003年1月15日
開催場所:財団法人ソフトウエア情報センター
要旨:情報テクノロジー(IT)の進展により各所で生じてきた情報の蓄積と著作権を調整するため、フェアユースと呼ばれるアメリカの包括的・一般的な著作権制限規定をわが国著作権法に導入するさいの論点等について報告したもの。
発表者名:駒田泰土
題名:「『属地主義の原則』の再考 — 知的財産権の明確な抵触法的規律を求めて — 」
学会名(講演会名):日本工業所有権法学会
発表年月日:2003年6月7日
開催場所:早稲田大学
要旨:以下の5点を骨子とする報告を行った。①わが実定法上、知的財産権についていわゆる「属地主義」をとらねばならない明確な根拠は存在しない。②このインターネット時代において属地主義に拘泥するならば、知的財産権の保護が不充分なものになるおそれがある。③いわゆるカードリーダ事件最高裁判決(平成14年9月26日判決、民集56巻7号1551頁)も、判決が示した定義通りの属地主義を承認していないと解される。④同最判における抵触法的判断全体が理論的にみて難がある。⑤知的財産権のために抵触法の構造的理解に即した明確な規律が与えられねばならない。そのさい、属地主義を無批判に前提とすべきではない。
[分担執筆]
執筆者名:駒田泰土
題名:「第2章 知的財産侵害訴訟における国際裁判管轄 フランス」
編著者名:木棚照一
書名:『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』
発行所名:経済産業調査会
発行年月日:2003年5月
分担執筆の頁:43〜56
要旨:標記の問題について、フランスにおける法実務の概略及び最新の学説等を紹介した。
執筆者名:駒田泰土
編著者名:木棚照一
題名:「第3章 知的財産侵害訴訟における準拠法 イギリス」
書名:『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』
発行所名:経済産業調査会
発行年月日:2003年5月
分担執筆の頁:173〜190
要旨:標記の問題について、イギリスにおける法実務の概略及び最新の学説等を紹介した。
執筆者名:駒田泰土
題名:「第4章 インターネットによる著作権侵害の準拠法」
編著者名:木棚照一
書名:『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』
発行所名:経済産業調査会
発行年月日:2003年5月
分担執筆の頁:293〜310
要旨:インターネットを介した著作権侵害事件の準拠法問題に関する諸学説をレビューし、いずれにせよ当該の問題を解決していく上ではいわゆる属地主義の原則の緩和ないし放棄が必要であることを論じたもの。国際著作権条約であるベルヌ条約の解釈についても一言した。
[その他]
主催者:群馬大学社会情報学部
タイトル:「IT社会における司法 — 法のエンフォースメントに対する情報テクノロジーの挑戦 — 」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年2月1日
要旨:群馬大学社会情報学部学内シンポジウム報告。法のエンフォースメントという観点に立って、情報テクノロジー(IT)がそれを阻害する具体的な要因とは何か、そしてかかる問題への対処としてどのようなものが考えられるかについて論じた。
主催者:一橋大学国際企業戦略研究科
タイトル:「知的財産権に関する最近の渉外判例の理論的検討 — 円谷プロ事件及びカードリーダ事件最高裁判決を中心に — 」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年6月25日
要旨:特許権の保護に関する国際私法的考察を一応提示してみせたいわゆるカードリーダ事件最高裁判決(平成14年9月26日判決、民集56巻7号1551頁)、請求の目的たる財産がわが国の著作権であるときはわが国に財産所在地としての裁判籍があるとして国際裁判管轄を肯定したいわゆる円谷プロ事件最高裁判決(平成13年6月8日判決、民集55巻4号727頁)についての理論的検討を行った。
主催者:栃木県立栃木南高等学校
タイトル:「インターネット上の名誉毀損」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年9月25日
要旨:平成15年度「栃南一日大学」の一環として行った出前講義。具体的には、インターネット上での名誉毀損について、実例をふまえながら、この問題をめぐる法の実際を平易に解説した。
主催者:群馬大学社会情報学部
タイトル:「いわゆるファイル交換ソフト問題が問いかけるもの」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年10月3日
要旨:群馬大学社会情報学部10周年記念シンポジウム報告。具体的には、いわゆるP2Pネットワークを介して行うファイル交換(共有)が提起している著作権問題及び今後の課題について論じた。
主催者:群馬大学
タイトル:「インターネット上の名誉毀損 — 毒づくのは(楽しいけど)ほどほどに — 」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年10月11日
要旨:群馬大学平成15年度公開講座である「情報化の今を生きるための法律・政策講座」の一環として行った講義。具体的には、インターネット上での名誉毀損の成否やサービス・プロバイダの責任等について平易に解説した。
主催者:文化庁
タイトル:「著作権分科会報告」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年10月31日
要旨:文化審議会著作権分科会国際小委員会で行った報告。インターネットを介した著作権侵害の国際裁判管轄問題・準拠法問題の構造について平易に解説した。
主催者:大阪大学大学院法学研究科
タイトル:「職務創作の国際私法上の問題」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年11月6日
要旨:大阪大学大学院法学研究科が主催する産学連携公開講座の一環として行った講義。具体的には、各国の特許法・著作権法上の職務創作制度をめぐる法の抵触問題とその解決について、実務家向けに専門的な解説を行った。
主催者:北海道大学大学院法学研究科
タイトル:「知的財産法と属地主義について」
講演者名:駒田泰土
日程:2003年12月20日
要旨:北海道大学大学院法学研究科内に設置された知的財産法研究会での研究報告。内容的には、2003年6月17日における日本工業所有権法学会報告をベースとし、若干のアレンジを施したもの。
経済・経営情報講座
経営情報システム研究室
[学会等での発表]
発表者名:田村 泰彦
題名:10年後の人間中心型ITへの期待
学会名:第8回日本社会情報学会大会
発表年月日:2003年10月19日
開催場所:熊本学園大学
要旨:現在のコンピュータおよび通信に係わる関連技術はまだまだ問題が多く、我々のようなIT利用者は多くの問題に直面している。ここでは、それらの問題点について分析し、それらが解決されれば人間はどのようにコンピュータを使って、日常の問題に対処出来るようになるかを予測する。
会計学研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:中島照雄
題名:エージレスソサイエティの経営会計システムの一考察システム
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究録集
号数:第10巻
発行年月日:2003年3月31日
頁:151〜169
要旨:日本の人口は、世界に類をみないスピードで高齢化が進行しており、社会に深刻な影響がいろいろと及ぼしている。日本の企業経営の大きな特徴である終身雇用および年功序列の制度があるが、近年、その制度も大きく変わりつつある。
ここでは、日本の高齢社会概観(高齢者世帯の所得と支出、労働、社会福祉)や生涯現役社会の概念、雇用システム改革、高齢化の量と質の変化、定年制と採用時の年齢制限(「日本版年齢差別禁止法(仮称)」の策定)、高齢者就業や起業などに係る今後の課題、高齢化とノーマライゼーション、少子化社会と子育ての社会化(「少子化社会対策基本法(仮称)」の策定)、世代間利害対立の緩和と高齢者のインフラ整備などの展開を通して、生涯現役社会での今後の経営会計システムの基本概念を論じる。
[学会機関誌等への投稿]
著者名:中島照雄・川名子敬至
題名:知的財産の評価と経営会計システムの一考察
掲載誌名:足利工業大学研究集録
号数:第36巻
発行年月日:2003年3月31日
頁:29〜34
要旨:知的財産を国家戦略として保護・強化を目的とする「知的財産基本法(2002 年11月27日)」が成立した。そこで、大学や企業に対しては、知的財産から適切な収益を得るための管理・運用の責任や、研究者の職務が魅力的とうつるような適切な処 遇の確保などを義務として問われている。
ここでは、知的財産の概念や知的財産の評価、知的財産の経営会計システム(財務会計上の評価、財務諸表上の表示など)、さらに知的財産の経営会計システムでの諸問題などの展開を試みている。
[その他 — 講演]
講演者:中島照雄
題名:非営利組織会計
講演会名:市民立NPOカレッジ(ハローワークから受講指示又は推薦をされた方を対象)
講演年月日:2003年7月1日
開催場所:群馬県勤労福祉センター(群馬県前橋市)
要旨:雇用保険受給中に公共職業安定所長から受講指示を受けた方(ハローワークから受講指示又は推薦をされた方)を対象にして、NPO法人の運営・起業に関する全般的な知識を習得する研修の一つである。
ここでは、諸処の非営利組織体の概要や、公益法人とNPO法人の経営、NPO法人会計システム、NPO法人の今後の経営の課題などを展開した。
[その他 — 講演]
講演者:中島照雄
題名:環境会計の現状と展開
講演会名:群馬大学社会情報学部10周年記念シンポジウム
講演年月日:2003年10月3日
開催場所:群馬大学社会情報学部(群馬県前橋市)
要旨:持続可能な発展を目指し、経済体制を維持していくには環境と経済の連携は不可欠である。環境会計は環境と経済を連携させる一つのツールで、環境会計の使命は環境保全活動と経済活動を結び付けることである。現在、環境報告書の発行企業は600余社、環境会計は500余社になっている。環境報告に関しては情報開示の法制化は未だない。今後は、第三者機関による環境報告書の審査登録を法制度化する「環境経営促進法(仮称)」などの策定も必要になる。環境と経済の連携に関して、今後の企業経営の課題を展開した。
経営学研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:寺石雅英
題名:証券投資法人を活用した県民直接参加型地域振興モデル —地域ファンドを有効に機能させるために—
掲載誌名:中小公庫マンスリー第50巻第4号
巻数:第50巻
号数:第4号
発行年月日:2003年3月31日
頁:6〜11頁
要旨:ここ数年全国各地で設立が相次いでいる地域ファンドの多くは、自治体と地元金融機関・有力企業が出資者となり、運営をベンチャーキャピタルに委託する、いわば「丸投げ型スキーム」によるものである。本稿では、従来とはタイプの異なる、市民直接参加型の地域ファンド「ゆめファンド in ぐんま」の創設に向けた動きを紹介しながら、地域ファンドが有効に機能するための条件について考察した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:起業家の意思決定バイアスとベンチャー倒産
学会名(講演会名):第12回日本MITエンタープライズ・フォーラム
発表年月日:2002年10月26日
開催場所:三菱総合研究所
要旨:起業家を対象に、ベンチャー企業が陥りやすい意思決定バイアスに関して注意を喚起するとともに、それを回避するための手段について論じた。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:ベンチャー倒産に学ぶ経営判断の罠
学会名(講演会名):ベンチャーフェアJAPAN2003
発表年月日:2003年1月16日
開催場所:東京ビックサイト
要旨:ベンチャー倒産の大部分が、経営者が意思決定バイアスに陥ることを原因としたものであることを明らかにするとともに、意思決定バイアスに起因する倒産を回避するためにはそのような点に注意すれば良いのかについて説明した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:エクイティ手法を活用した自治体経営
学会名(講演会名):地域開発とベンチャービジネス振興研究会
発表年月日:2003年1月24日
開催場所:新潟大学大学院現代社会文化研究科
要旨:これまでは自治体が手がけてきた事業の一部もしくは大部分を、自治体、市民、地元企業等の共同出資によって設立した持株会社の傘下のプロジェクトカンパニーとして運営するとともに、持株会社および各カンパニーがそれぞれ株式公開を目指すという、地方税や地方交付税によらない、まったく新しい地域振興モデルを提示した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:ベンチャー倒産に学ぶ経営判断の罠
学会名(講演会名):群馬積水ハイムグループSHT会2月度定例会
発表年月日:2003年2月27日
開催場所:前橋テルサ
要旨:ベンチャー企業の倒産の大部分が、意思決定バイアスに起因するものであることを明らかにするとともに、意思決定バイアスに陥らないための方法を提案した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:片想いはなぜ長続きするのか? — 現状に固執する経営判断の罠 —
学会名(講演会名):商工中金群馬中金ユース会
発表年月日:2003年7月2日
開催場所:前橋東急イン
要旨:中小企業経営者が陥りやすい経営判断の罠を紹介するとともに、場合によってはそれが企業倒産にもつながりかねないことを、実例を用いながら明らかにした。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:21世紀の自治体経営のあり方 — 自治体持株会社化モデル —
学会名(講演会名):白鴎大学大学院講座「北関東圏の発展と自治体経営」
発表年月日:2003年7月5日
開催場所:白鴎大学
要旨:これまでは自治体が手がけてきた事業を、自治体、市民、地元企業等の共同出資によって設立した持株会社の傘下のプロジェクトカンパニーとして運営するとともに、持株会社および各カンパニーがそれぞれ株式公開を目指すことにより、地方税や地方交付税によらないまったく新しい財源の確保、市民の資産形成、地元企業の業務効率化や資金調達能力の向上に直結させる地域振興モデルを提唱した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:意思決定の罠に陥っていませんか?
学会名(講演会名):大泉教員研修連続ワークショップ
発表年月日:2003年8月5日
開催場所:大泉町社会福祉会館
要旨:教員を対象に、教育現場に発生しやすい意思決定バイアスについて取り上げ、それによる悪影響を回避し、逆にそれを有効に活用するための手段について明らかにした。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:いかにして中小企業を元気にするか? — 今こそ中小企業変革の時代 —
学会名(講演会名):AKK互助会総会記念講演会
発表年月日:2003年8月8日
開催場所:前橋商工会議所
要旨:潜在的な実力ありながら飛躍できない群馬の中小企業セクターを活性化するための方策として、イタリア型産業集積プロジェクトを提唱した。
[学会等での発表]
発表者名:寺石雅英
題名:商業高校はベンチャー教育で甦る
学会名(講演会名):平成15年度群馬県公立高等学校商業科主任研修会
発表年月日:2003年8月26日
開催場所:上毛会館
要旨:ブランド価値の崩壊が著しい商業高校の復活の決め手が、ベンチャー教育にあることを明らかにするとともに、商業高校に期待されるベンチャー教育とはいかなるものであるのかを考察した。
理論経済学研究室
[論文等]
著者名:Takashi YAGI
論題:"Evaluation of Economic System PartⅠ: Value and Distribution (the first draft)"
提出場所:ローマ大学第3、経済学部、スラッファ研究センター
提出年月日:2003年3月31日
概要:ローマ大学第3、経済学部スラッファセンターに客員研究員(Visiting Scholar)として滞在した際の研究報告書。価値と分配に関する以下の論文をまとめた。
"Smith and Sraffa : Continuity in the Labour Standard"
"Sraffa's System and AlternativeStandards"
"A Surplus Interpretation of the Sraffa System"
尚、本稿はローマ大学第3、スラッファセンターで利用可能(公開)である。
著者名:Takashi YAGI
論題:"Evaluation of Economic System PartⅡ: Intertemporal Comparisons of Value, Productivity and Income (the first draft)"
提出場所:ローマ大学第3、経済学部、スラッファ研究センター
提出年月日:2003年3月31日
概要:ローマ大学第3、経済学部スラッファセンターに客員研究員(Visiting Scholar)として滞在した際の研究報告書。異時点間比較に関する以下の論文をまとめた。
"Sraffa's System and Intertemporal Comparisons"
"Evaluation of Sectoral Productivity Changes"
"Real National Income: A Classical Approach"
尚、本稿はローマ大学第3、スラッファセンターで利用可能(公開)である。
著者名:八木尚志
論題:「部門別生産性変化と社会的生産性変化の多期間比較の方法」(全5頁)
誌名:The 14th Conference Reports, PAPAIOS(環太平洋産業連関分析学会),58-62頁
発表年月日:2003年11月1日
概要:本稿では、八木[1998]以来発展させてきた2期間の場合に考案された生産性指数ないし所得指数を多期間の場合に拡張する方法、および八木[2002]によって明らかにされた部門別生産性変化の指標を検討し、多期間比較のための所得指数、生産性指数、通時的標準商品、通時的標準労働、部門別生産性変化度という新たな概念を提案した。
[国内学会・研究会報告]
発表者名:八木尚志
論題:「部門別生産性変化と社会的生産性変化の多期間比較の方法」(全15頁)
発表学会:第14回環太平洋産業連関分析学会年次大会、熱海、起雲閣
発表年月日:2003年11月1日
概要:[論文等]の項目を参照
発表者名:八木尚志
論題:「多部門生産モデルと集計量分析」
発表学会:ポストケインズ派研究会、早稲田大学
発表年月日:2003年12月13日
概要:多期間比較のための生産性指数、所得指数、通時的標準商品、およびそれらの指数を取り込んだ賃金曲線の性質とそれに対応する資本概念、等について論じ、さらに私のアプローチとPasinetti教授のアプローチの対比を行った。
発表者名:八木尚志
論題:「不変の価値尺度とスラッファ」
発表学会:リカードウ研究会、明治大学
発表年月日:2003年12月24日
概要:スラッファ体系における標準純生産物=総労働量の関係の意味、および古典派、特にA.スミス、D.リカードウの価値尺度に関する考え方との関係、等について論じた。
[国際学会・セミナー報告]
(報告)
発表者名:Takashi YAGI
論題:"Sraffa's System and Alternative Standards", (全44頁)
発表場所:ローマ大学第3、経済学部、スラッファセンター
発表年月日:2003年1月29日
概要:ヨーロッパ経済学史学会2001年度大会(ESHET 2001 Conference)で報告された同名の報告論文を加筆修正し報告した。本稿は、ローマ大学第3、スラッファセンターで利用可能(公開)である。
発表者名:Takashi YAGI
論題:"Real National Income: A Classical Approach"
発表学会:International Conference on the Paradoxes of Happiness in Economics, University of Milan-Bicocca, Milan,
発表年月日:2003年3月22日
概要:論文 "Real National Income: The Hicks-Sraffa Approach" 早稲田大学現代政治経済研究所のワーキングペーパー(No.2001)を加筆修正し報告した。加筆部分は、標準賃金曲線、実質所得の購買力比較、実質賃金比較等の部分である。
発表者名:Takashi YAGI
論題:"The Reswitching Debate Revisited"
発表学会:Annual Conference of the History of Economics Society (HES 2003 Meeting) Duke University, USA
発表年月日:2003年7月5日
概要:技術の再転換論争の論点を、J.ロビンソン、サミュエルソン、ハーコート、ガレニャーニ、スラッファ等に関して整理し、そのモデルの問題点を明らかにし、私の考えである新たな賃金曲線(標準賃金曲線)では技術の再転換が生じないことを示した。尚、本稿の考え方は、邦語論文八木[2001]で論じられたものに若干の改善を加えたものである。
(指定討論)
報告者:Yosihiro Yamazaki
論題:"Francis Amasa Walker and a non neutral progress of technology"
討論者:Takashi Yagi
発表学会:Annual Conference of the History of Economics Society (HES 2003 Meeting) Duke University, USA
発表年月日:2003年7月7日
概要:山崎教授(福岡大学)の報告論文は、F. A. ウォーカーの経済理論をリカードウのモデルと関連させて解釈したものであり、その解釈に関して、1)資本の扱い、2)生産関数、等について討論を行った。
[一般講演]
講演者:八木尚志
論題:「やさしい経済学が解く日本経済」
講演場所:太田市八幡町公民館
講演年月日:2003年6月10日
概要:ケインズ流の景気対策の考え方と市場を重視する考え方を対比し、日本経済の現状理解について解説した。
経営管理研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:杉山学
題名:DEAに基づく入出力項目が連鎖したDMUの効率評価
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10
発行年月日:2003年3月31日
頁:171〜186
要旨:本論文では, DEA (Data Envelopment Analysis)モデルの概念に基づいて,入出力項目が連鎖したDMUの効率評価モデルを提案し, DMUの総合的な連結効率値を算出した.さらに, 効率改善のための統一的な改善案を導き出すことが可能となった.
[学会等での発表]
発表者名:杉山学,山田善靖,堀江貞之,中里裕樹
題名:日本の資産運用会社の経営効率性評価
学会名(講演会名):経営情報学会2003年秋季全国研究発表大会
発表年月日:2003年11月1日
開催場所:函館大学
要旨:日本の資産運用会社は欧米の資産運用会社に比べ長年低収益性に苦しんでいる.日本の資産運用会社の収益性が低い大きな原因は,運用報酬率が欧米に比べ低く,規模の経済を満たすほどの運用規模になっていないことがあげられる.運用規模以外に資産運用ビジネスを行う効率性の観点で,日本の資産運用会社をデータ包絡分析法(Data Envelopment Analysis : DEA)によって評価する.
計量経済学研究室
[学会機関誌等への投稿]
著者名:樋田勉
題名:有限母集団における累積分布関数の推定
掲載誌名:群馬大学社会情報学部研究論集
巻数:10
発行年月日:2003年3月31日
頁:187〜204
要旨:有限母集団における推論において、完全な補助変数が利用できる場合の累積分布関数推定量についてサーベイし、推定量の性質をシミュレーション実験によって比較検討した。
[学会等での発表]
発表者名:樋田勉
題名:有限母集団における累積分布関数の推定について
学会名:2003年度第71回日本統計学会
発表年月日:2003年9月2日〜9月5日
開催場所:名城大学天白キャンパス
要旨:標本調査の領域において、完全な補助変数が利用できる場合の累積分布関数の推定量について取り上げた。分布関数の推定量として、model-based推定量と、design-based推定量が提案されている。本報告では、主な推定量ついてシミュレーション実験を行い、それぞれの推定量の性質とジャックナイフ分散推定量の性質について報告した。
[分担執筆]
執筆者名:佐竹元一郎、野口和也、西郷浩、河田正樹、樋田勉
編著者名:佐竹元一郎
書名:マルチメディアと経済社会
発行所名:早稲田大学出版部
発行年月日:2003年3月20日
分担執筆の頁:116頁〜139頁
要旨:マルチメディア時代の中心的存在であるコンピュータに焦点をあて、デジタル技術で何ができるのか、また問題点は何かを考える。パソコンを中心とする「規格」の可否、インターネットにおける暗号、Webによる統計調査の公表に潜む問題、グラフィックスを用いた統計学教育などをテーマに、8編を分担執筆した。(第5章を担当)