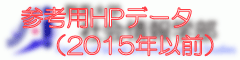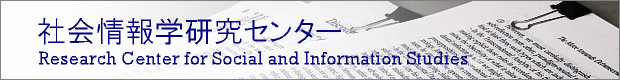
【以下にお示しするのは,過去に開催されたシンポジウムの資料です】
2010年度 社会情報学シンポジウムのお知らせ
|
2010年度 社会情報学シンポジウム 異 文 化 理 解 昨今日本全体が内向きになり,外国への留学生が漸減するなかで,学生・教職員の「異文化理解」をさらに深め,国際交流の活性化を図るべく,異文化理解に造詣の深い先生方を迎え,社会情報学シンポジウム「異文化理解」を開催いたします。
司会:砂川裕一(社会情報学部教授)
問い合わせ先: 群馬大学社会情報学部 TEL: 027-220-7403 このシンポジウムは平成22年度特別経費(運営費交付金)によるものです。 |
シンポジウム 演題 概要
斎藤佑史先生 「体験から学ぶ異文化理解 ― 海外研修引率者の目からみた」
異文化理解を目的とする東洋大学で実施されている一つの海外研修を紹介しながら問題点を考えます。採り上げる研修は,対象が経済学部の学生で出掛ける先は独仏です。百聞は一見にしかずというわけで,異文化理解のためには確かに異文化体験は欠かせませんが,異文化体験しても正しい異文化理解にかならずしも直結しているわけではありません。この問題を引率者の目から考えてみたいと思います。
杉野健太郎先生 「二つのアメリカ ― きわめて私的な経験から」
二つのアメリカ。保守的なアメリカと革新的なアメリカ,宗教的なアメリカと無神論的なアメリカ,あるいはアメリカの分裂という現象。しかし,マスメディアを通して異文化に接することが多いわれわれ日本人は,この二つのアメリカをどのように理解してきたのでしょうか?きわめて私的で学問的には仮説に満ち満ちた話ですが,それを1961年生まれの私自身の経験からお話ししてみたいと思います。それは,ソクラテスの言う「無知の知」,換言すれば,異文化と辛抱強く対話することの必要性を理解する過程でもあります。この姿勢は,異文化理解だけではなく,学問においても必要な姿勢かもしれません。
守時なぎさ先生 「<クリック> を越えた <異文化理解>」
スロベニアの日本研究をする学生の多くは,日本のポップカルチャーに興味を持って入学してきます。ところがスロベニアでは一般日本人との接触がほとんど無く,「日本文化」といえば学生たちが「クリック」する情報に限られています。このような環境の中で,学生はどのように日本文化を理解していくでしょうか。日本語を教える教育現場からの試みを紹介しながら,「異文化理解」の可能性について皆さんと考えていきたいと思います。
阿部美里さん 「イタリア留学記 ― フィレンツェからヨーロッパへ」
群馬大学在学中,イタリアのフィレンツェ大学へ一年間の交換留学をしました。留学したいと思った動機,留学に至る経緯,フィレンツェでの留学生活,留学から帰った後の進路など,留学にまつわるエピソードをご紹介しようと思います。最近,留学してみようという人は減少しているようです。そんな中,留学という長期滞在をすることによって得られる異文化理解の楽しさや,人生における貴重な経験知を高めるといったメリット,また就職活動においての有利さなどについても触れてみたいと思います。