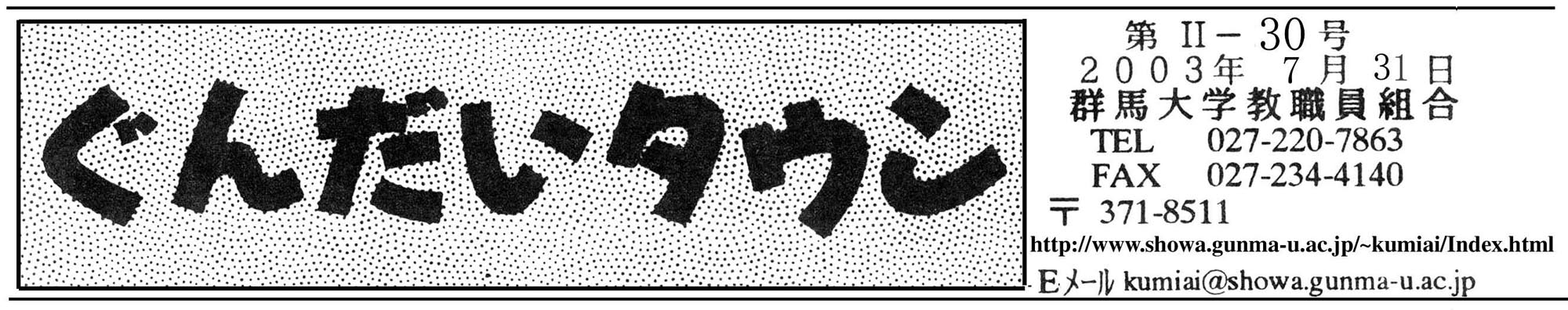
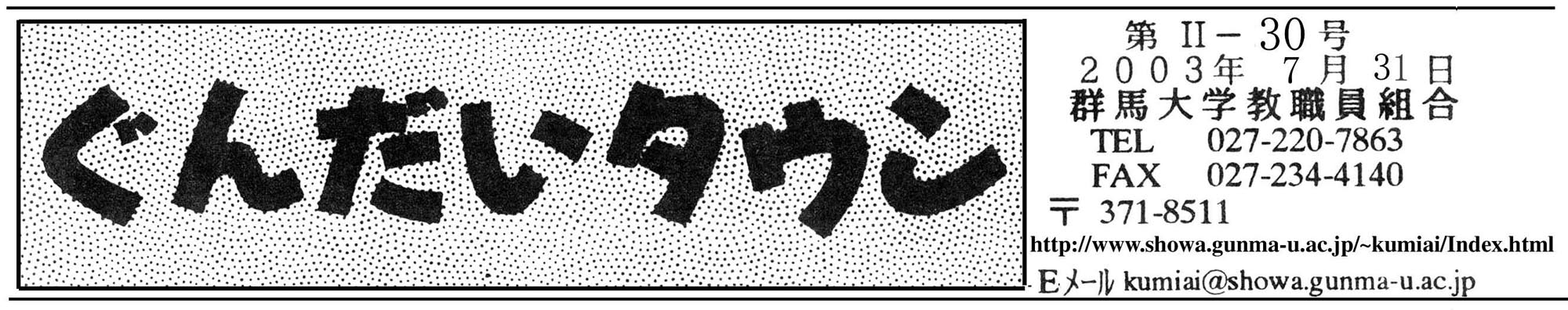
|
|
○激動の時代に立ち向かう組合を、皆の力で
 執行委員長 齊藤隆夫
執行委員長 齊藤隆夫
文部科学省が会期内の成立を疑いもしなかった「国立大学法人法」(案)が、延長国会の期限あと少しという今の時点でも成立していない。こうした状況を作り出したのは、法案の内容があまりにひどすぎるという事情もあるが、全大教を中心とした国立大学の将来を憂う知識人・文化人のこの間の運動であることは間違いないと思われる。この原稿が「群大タウン」にのって組合員の皆さんの目にとまる頃には、あるいは法案は通ってしまっているかもしれないが、こうした状況を作り出せたことに組合は少しは自信を持っても良いのではないか、と思う。
しかし、もし法案が通った場合にわれわれ国立大学に働く者の前に立ち現れる状況は当に激動と言うべきであろう。その詳細をここで述べる必要はない。その概要は、すでに、前の執行部が数次のニュースで伝えてくれている。そこで、私たち新執行部の仕事はそれに立ち向かいつつ、さらに強力に立ち向かうことのできる組合を作っていくことであろう。課題は沢山ある。新法のもとで危惧されている基礎的な自然科学研究や文化の薫り高い人文・社会科学の衰退を防ぐこと、様々な雇用形態の非常勤職員をはじめとして教職員の雇用と・労働条件を守ること等々。私たち新執行部はこの課題に持てる力を可能なかぎり発揮して、取り組んでいきたい。
総ての組合員とこれから組合員になられる方のご協力とご支援を、切にお願いしたい。何時か一緒に旨い酒を飲みましょう!
○組合 新しい時代に対応する体制に 定期大会開かれる
特別決議採択・齋藤委員長など新役員承認
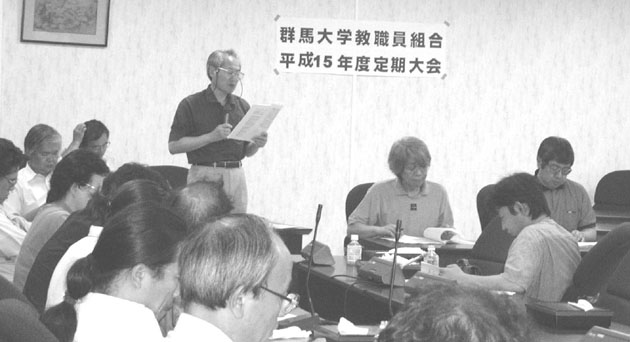

大会を進行する旧執行部役員と議長団

熱心に討議を行う代議員のみなさん
さる6月19日、昭和キャンパス医学部会議室にて、群馬大学教職員組合の定期大会が開かれました。本年度の定期大会では、昨年から問題となっていた埼玉大学との統合問題については、組合では埼玉大学教職員組合と共催でシンポジウムが行われたことや、本学でも本組合と生協との共催で2回の討論集会がおこなわれたことなどが、紹介されました。また、法人化は私たちの地位や労働条件に大きな影響を与えるので、労働協約をどのようなものすべきなのか?!といった具体的な問題について取り組みがおこなわれたことなどが紹介されました。さらに、法人化に際して大学当局は就業規則を作成する必要があり、その際に過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。組合は就業規則を通じた労働条件の決定に関して重要な役割を果たすべく、過半数の教職員を代表して就業規則の協議相手となるように努力を重ねていくことが確認されました。これらの議論を通じて、ますます組合の重要さが浮き彫りになってきました。
昭和キャンパスでは地道な取り組みが実を結び、すでに退職に伴う脱退者数を上回る新しい組合員を迎えていることが、紹介されました。さらにこんな時代だからこそ組合に!!という趣旨の全教職員にむけた特別決議も採択されました。2003年の取り組みとして、何としても全員の雇用継続と労働条件の改善をせまれる組合をつくること、全教職員のなかに飛び込んで組合への加入を働きかけること、法案審議で明らかとなった諸問題を踏まえ、必ず本年度中に充分な手当てをおこない、現在の違法状態をもちこまないよう当局にせまって行くこと、などの提案がなされ承認されました。


ご存じの通り、7月9日に、「国立大学法人法案」等の関係6法案が、参議院本会議で可決され成立しました。私たち群馬大学教職員組合では、法案の問題点を指摘し、全国の数多くの大学人とともに法人化に反対してきました。最近では、国会の審議を通じて法案の問題点がますます明確になり、マスメディア等でも法案に対する批判の声が多く聞かれるようになってきていました。法案が国立大学を文部科学省に従属させようとしていること、日本の教育・科学の将来を大きく損なうものであることが、広く認識されるようになってきていたのです。そんな中で、それを無視するかのように法案が採決に付され可決・成立したことには、大きな失望と強い怒りを感じざるを得ません。私たち群馬大学教職員組合は、ここに抗議の声明を発表します。是非とも、ご一読ください。
7月9日、「国立大学法人法案」「独立行政法人国立高等専門学校機構法案」等関係6法案は、参議院本会議で可決され成立した。 この間、衆議院で5回、参議院で7回の委員会審議が行われ、法案に数多くの重大な問題のあることが明らかになった。にもかかわらず政府は、批判にまともにこたえず、「来年4月に法人化」という政府の日程のみを優先し、与党の数の力で審議不十分のまま法案を成立させたものである。私たちは、小泉内閣と与党に対し、強い怒りと抗議を表明する。
この「国立大学法人法」には、次のような問題がある。
(1)「法人化し、自律的な環境のもとで国立大学をより活性化する」との謳い文句とは裏腹に、文部科学大臣が大学の中期目標を定め、中期計画を認可し、大臣の変更命令に従わなければ罰金を科せられる。さらに、6年後に教育研究の門外漢である総務省の勧告をうけて、文部科学大臣が「廃止や民営化」を含む措置をとるのである。
(2)国立大学の第一次的な財政責任を負うのは「国」から「法人」に移ることになり、学費など国民負担が増える危惧がある。さらに財務・会計制度に関する具体的な事項は、これから定められる政令・省令に委ねられ、この期に至っても運営費交付金の配分基準すら示されていない。群馬大学の場合で340億円にも膨れ上がってしまった大学法人の債務をどう解消するかは不明確であり、大学における教育・研究・医療の水準を維持改善するに足る公費が確保される保障はどこにもない。
(3)教員が公務員でなくされることにより教育公務員特例法が適用されなくなり、教員人事の自主性が脅かされるおそれがある。このことは大学自治を損ない、ひいては学問の自由を掘り崩すことにつながる。そして、大学の教育・研究・医療が一部の人のためのものに変質し、大学が社会に対して果たすべき責任を果たせなくなってしまいかねない。
(4)経営と教学を分離し、学外者が多数を占める経営協議会に大きな権限を与えながら、教育研究評議会には予算や組織改廃の審議・決定権を認めていない。これは、教育研究を目的とする大学の運営組織を、経営効率優先の組織に変質させるものである。
(5)「学長選考会議」は、経営協議会の学外委員及び教育研究評議会選出の委員、各同数で構成され、委員総数の3分の1以内で学長・理事を加えることができるとしている。これでは、大学運営の最高責任者の決定を、学外委員(文部科学官僚の天下りも予想される)の意向が左右する危険がある。
(6)法人化によって労働安全衛生法等が適用されることとなる。だが、国立大学の数多くの施設が同法の基準に反する状態であり、それにもかかわらず適法にするための補正予算は予定されていない。したがって、来年4月には違法状態が頻出する。これまで、同法が適用されないのをいいことに安全衛生のための措置を怠ってきた文部科学省の責任は、非常に重大である。
国会、とりわけ参議院における法案の審議を通じて、これらの問題点が明確となった。遠山敦子文部科学大臣をはじめ文科省官僚は、失言、暴言、無関係な答弁を繰り返し、審議がたびたびストップした。また参議院において23項目もの附帯決議が採択されたことは、同法がいかに欠陥に満ちているかを物語っている。なお、この付帯決議は、上のような問題点が最悪の形で顕現することを阻み、学問の自由と大学自治の擁護、教職員の身分保障と待遇改善を図る今後のとりくみをすすめる上で、権限濫用等の歯止めとして活用しうるものであり、それを生かせるかどうかは全大学人の今後の努力にかかっている。
法案が成立した今、大学・高等教育の充実をめざす私たちの前途には多大な困難が待ち受けている。しかし、いかなる困難があろうとも、私たち群馬大学教職員組合は、人類と地域社会に貢献する大学・高等教育の再構築に向けて、また、地域の方々と群馬大学の構成員の絶大な支援のもとに、群馬大学の教育・研究・医療の後退を許さずに充実させていくために、今後とも努力を重ねていく決意である。また、そのためにも、群馬大学のすべての教職員の身分と権利を確保するための取り組みをいっそう強めていく所存であることを、あわせて表明する。


大学法人法の問題点や天下りの危惧やその財源の危うさを伝える新聞や意見広告
○労働安全衛生対策は追加財政なしで ? --------- 文科省が信じられないような責任放棄を指示??
すでに明らかになっているように、国立大学が法人化すると労働安全衛生法等の法律が適用されるようになるので、労働者の安全・健康の面から大学の施設が労働基準監督署の指導の対象となり、劣悪な研究室の状況が労働安全衛生法に違反する事態となります。その対策の一環として、桐生キャンパスでは産業技術総合研究所・環境安全管理部の飯田光明氏、昭和キャンパスでも労働基準監督署OBでコンサルタントの干川隆一氏を招いての講演会が、大学当局により開催されました。
講演では、私立の大学に準じての適用ならば、建物には必ず2箇所以上の避難経路を設けなければならないこと、廊下に物を置くことは許されないこと、古い建物でも床からの漏水はあってはならないこと、エーテル・メタノールなど引火性の危険物やアジ化ナトリウム・ピクリン酸など爆発性危険物を扱う研究室には必ずドラフトがなければならず、保管庫には排気装置が必ず必要であること、排液などの貯蔵はできずすぐに処理しなければならないことなど、大まかなことが、説明されました。
ところで、昭和キャンパスで事務からまわってきた印刷物には、「職員一人一人が安全義務を守らなければ罰則の対象になります」と書かれていました。けれども、法律の規制の内容のほとんどは施設に関することであり、上でみたように大学での安全衛生上の重要問題は施設・設備に関係しています。ですから、職員が罰則の対象になるかのような説明は誤解を招くものといわなければなりません。
そもそも、労働安全衛生法は、労働災害や職業病の危険から労働者(大学でいえば教職員)を守ることを目的とする法律であり、そのために事業主等に一定の義務を負わせています。同法の中で、労働者に義務を負わせる規定は一部にすぎません。施設の不備について労働者が責任を問われるいわれはなく、事業主の責任になります。つまり罰則(刑罰)の対象になるのは、事業主すなわち大学当局ということになります。
今回の事態は、明らかに教育研究条件の整備を長年にわたり放置してきた文部科学省の責任です。ですから、当然のことながら文部科学省が補正予算などの財政措置をとってその財源を確保すべきところです。ところが、文部科学省は、全国の国立大学の経理部課長を集めて、なんと、国は財政措置をとらないので各大学の学内経費のやりくりで「安全衛生対策を何が何でも今年度中に完了して欲しい」旨の「説示」を行いました(詳しくは下記の通りです)。
群馬大学では、法人化準備経費捻出のため、学部等基盤校費、共通教育経費、共通管理経費は昨年と同額の配分とし、教育研究重点経費は今年度は配分しないことが、通知されていますが、国立大学の安全衛生対策には、一時は国会で副大臣が補正予算を口にしたほどの大規模な経費を必要とします。それを、個々の大学の、しかも今年度予算で対応できるはずはありません。東大工学部のみでも17億円を優に超えるという経費を、文部科学省からの経費なしでどうやって補填するというのでしょうか。
文部科学省の積年の怠慢のツケがまわってきて、今、各大学の教育研究を浸食するような異常な事態が生じようとしています。そして、群馬大学当局も、このような文部科学省の、違法状態を放置するような方針に従おうせず、当然予算をつけるように要求すべきです。
---------------------------------------------------------------------------------------
「文教速報」2003.5.23付(第6463号)10頁
安衛対策は追加財政支援なしで緊急に改善を--------------舌津計画課長、全国経理部課長会議で要請
先の全国経理部課長会議で、文教施設部の舌津計画課長は「国立大学等の施設整備について」の説明の中で、安全衛生管理対策実施状況調査を5月16日付で緊急依頼したことを明らかにし、不備がある場合は今年度中に完了させるよう強く要請した。その際、追加財政支援はないという前提で、改善計画を立て、学内における財政支出を用意するよう求めた。
財源として考えられるのは、示達済みの施設整備費と学内経費の充当。舌津課長は「安衛対策が緊急に必要とあれば、示達済みであろうとも、先にやらなければならない。学内経費については、学長裁量経費、競争的研究資金の間接経費、それに営繕費が考えられる。こういうものを総動員して、安全衛生対策を何が何でも今年度中に完了して欲しい」と説示を行った。
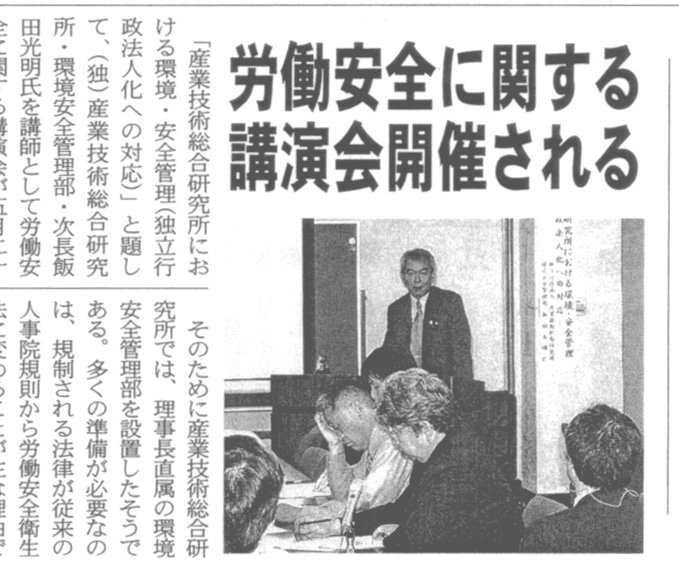 講演会の内容を伝える工学部ニュース
講演会の内容を伝える工学部ニュース
おまけのページ 「法人化でどうかわるの?」
Q 組合にはいってメリットはあるの?
Ans. 法人化されると民間企業と同じ世界になりますから、組合に入ると入らないとでは、自分の給与や労働条件の決定に関与する可能性がまったく違ってきます。 また、大学が法人化されると給与にせよ予算にせよ、色々なところに評価と競争が入ってきます。部局の改編や大学の経営戦略の変更が、配置転換や雇用調整にむすびつく可能性も、これまでよりはるかに大きくなります。評価や競争の公正さや、配置転換や雇用調整のルールについて、経営する立場とは別にはたらく当事者の立場からチェックし、改善させることが必要です。
こうした場合に、労働組合はメンバーひとりひとりの基本的な権利をバックアップし、納得のいく結果を求めて交渉することができます。一人で大学と交渉するのはたいへんですが、窓口として組合を使うことができれば、ぐっとやりやすくなります。賃金や労働条件について、労働組合が申し入れた団体交渉には、使用者は応じる法的義務があります。労働組合とは、自分がはたらくルールの決定や運用に参加するためのしくみなのです。
Q 法人化してから、組合に入るかどうか考えれば良いのでは?。
Ans. 今後職場のほとんどのルールを決める就業規則や労使協定など、最初の制度づくりと当初の労働条件の決定は、法人発足の以前に決まることになります。公務員の勤務時間や休暇制度は、労働基準法の基準よりもかなり有利なものなのです。
たとえば結婚、災害、不可抗力、忌引き、配偶者出産、夏季などの特別休暇や病気休暇は、労働協約か就業規則にあらためて定めないと、すべて消滅してしまいます。ですから、当局と交渉することができる職員組合に、いま加入していただきたいのです。

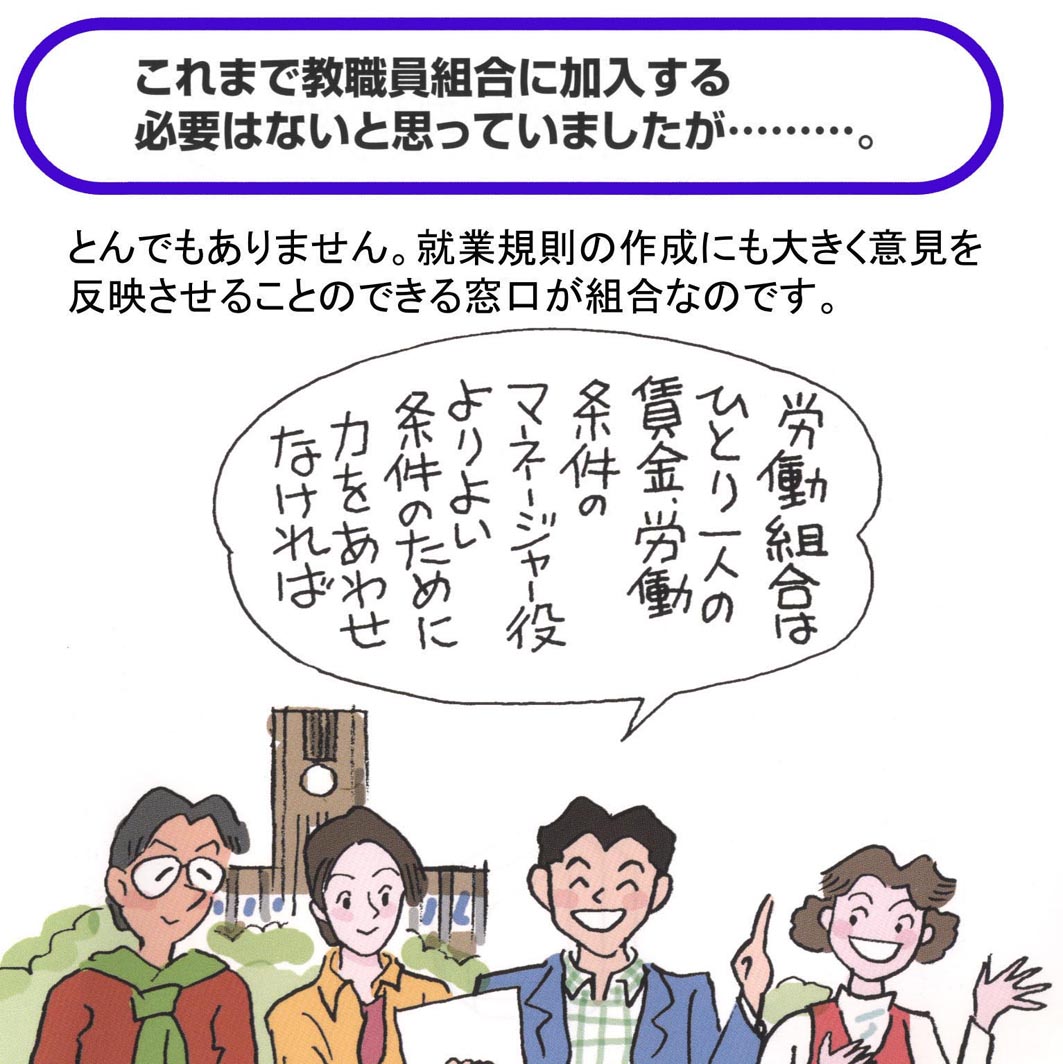
(全大教パンフレットより転載)
これからは中期計画の内容に沿って、法人の長(群馬大学は学長)と、直接交渉することになります。