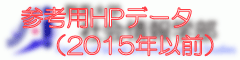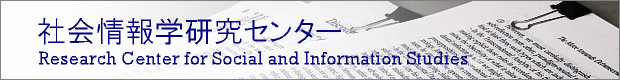
【以下にお示しするのは,過去に開催された講演会の資料です】
講演会のお知らせ
「水俣病」の経験から何を学ぶか
「私と水俣病」─ 患者さんのお話から
- 開催日時:2013年7月2日(火)13:00〜15:00
- 会場:群馬県前橋市荒牧町4-2 群馬大学荒牧キャンパス(ミューズホール)
※ 荒牧キャンパスへの交通アクセスについては,交通アクセスのページをご覧ください。
趣旨
公害の原点といわれる水俣病が公式に確認されたのは、経済白書が「もはや戦後ではない」と謳った1956 年5月1日のことです。公式確認から57年を経た現在もなお、水俣病の問題は解決をみません。水俣病が公害の原点と呼ばれるのは、単に規模が大きかったとか、悲惨であったという理由だけではありません。人間の生産活動の結果、環境が汚染され、汚染された魚介類の食物連鎖により、人間がメチル水銀中毒になるという、この発生のメカニズムが人類初の経験であったからです。とくに胎児性水俣病の発見は、人類の未来を象徴する衝撃的な事件でした。それは、母体は環境であり、環境を汚染することは、胎児(未来の命)を汚染することであると示したのです。胎児性水俣病の患者さんが、その存在を通して発信し続けているこの大切なメッセージを、私たちはきちんと受け止めてきたのでしょうか。
胎児性水俣病を発見し、水俣病の患者さんたちに寄り添い続けた医師の原田正純さん(故人)は、「水俣は鏡である。その鏡は、みる人によって深くも、浅くも、平板にも立体的にも見える。そこに、社会のしくみや政 治のありよう、そしてみずからの生きざままで、あらゆるものが残酷なまでに映し出されてしまう」と書いています。福島第一原発事故を経験した私たちは、いま一度、水俣という鏡から映し出される自分自身に向き合うことが必要なのではないか、そのような思いから本講演会を企画しました。どうか水俣という鏡に自分を映してみて下さい。そこに、どんな「自分の素顔」が映し出されているのか、それを読み取る力が、問われているのです。
プログラム
松永幸一郎さん(水俣病患者)
加藤タケ子さん(社会福祉法人さかえの杜・共同作業所ほっとはうす施設長)
猪原克敏さん(社会福祉法人さかえの杜・共同作業所ほっとはうす職員)
コーディネーター:群馬大学社会情報学部教授 西村 淑子
主催:群馬大学社会情報学部附属社会情報学研究センター
共催:宇都宮大学国際学部多文化公共圏センター
お問い合わせ先
群馬大学社会情報学部行政法(西村淑子)研究室
- 電話/FAX: 027-220-7492(電話/FAX 共通です)
群馬大学社会情報学部総務係
- 電話: 027-220-7403